解体工事現場の近くを通る時、「モノが落ちてこないかな」「がれきが倒れてこないかな」と少し不安になってしまいませんか?
それは、過去に解体工事現場で起こった事故のイメージが原因かもしれません。
現在は、建物を一気に壊すミンチ解体が主流だった頃と比べると、解体工事による事故は減少しています。
とはいえ、近年でも解体工事現場での事故が報道されることがあるため、これから解体工事を検討されている方は心配になってしまいますよね。
そこで、今回は過去に起こった事故の事例から、これからの安全な解体工事のための対策をご紹介します。
実際に起こった解体工事の事故事例
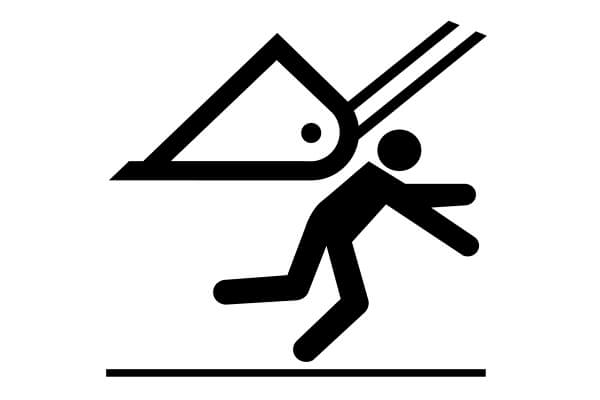
解体工事では、大型の重機を使用したり高い場所で作業をしたりするため、時に危険が伴うことがあります。
中には、作業員の方や通行人の方が命を落とされたケースも存在しますので、その事故事例を見ていきましょう。
労基署解体現場で重機横転、作業員死亡
東京・墨田区の労働基準監督署の庁舎の解体工事現場で重機が転落し、操縦していた作業員の男性が死亡しました。
13日午後、墨田区東向島の労働基準監督署の庁舎の解体工事現場で、鉄筋を運んでいた重機がバランスを崩して横転し、およそ1メートル下に落下しました。救急隊が駆けつけたところ、操縦していた58歳とみられる作業員の男性が操縦席に閉じこめられていて、病院に運ばれましたが、その後、死亡しました。「ドスンという音だった。消防車とかが来て、見たら重機が前に倒れていた」(近所の人)
重機は、鉄筋を挟んだアームを振った際にバランスを崩し、横転したとみられています。警視庁は、業務上過失致死の疑いも視野に、工事の責任者などから事情を聴いて事故の原因を調べています。※大元の記事は削除されています
こちらは、2015年5月に発生した事故です。
鉄筋を挟んだ重機がアームを動かした際にバランスを崩して横転してしまい、操縦していた作業員男性が操縦席に閉じ込められました。
こういった重機の横転や転倒による事故は全国各地で発生しており、各解体業者の意識改善が求められています。
これを受けて、「定期的な重機のメンテナンス」「十分な敷地の広さの確保」「勾配の角度調整」「作業計画の作成」など、徹底した対策に努める解体業者が増えています。
解体業者に工事を依頼する際には、過去の施工事例もチェックして、安全対策をしっかり行っているかを確認しましょう。
落下したコンクリートの下敷きに 男性作業員が意識不明
7日午前11時55分ごろ、戸田市美女木2丁目の美女木小学校東側歩道の下水路の工事現場で、さいたま市桜区の男性土木作業員(35)が落下してきたコンクリートの下敷きになったと119番があった。男性は川越市内の病院に搬送されたが、頭と胸を骨折するなどして意識不明の重体。
蕨署によると、男性は同日午前9時から、同じ会社の作業員とともに「ボックスカルバート」と呼ばれる箱状下水路の解体工事を行っていた。別の作業員が発見した際、男性は上から落下したとみられる縦約125センチ、横約110センチ、厚さ約20センチのコンクリートの下敷きになっていたという。
こちらは2016年1月に発生した事故です。コンクリートが落下するかもしれない地点に作業員男性がおり、落下に巻き込まれてしまった事件とみられます。
ボックスカルバートとはコンクリート造の水路のことで、四方をコンクリートで固められているため、解体の際には注意が必要です。
解体工事の際、崩れるおそれのある危険な地点や、廃棄物を運び出す際に落下するおそれのある地点に作業員が近づくには細心の注意が必要になります。
壁を倒したり崩したりする際には作業員全員が把握できるように合図を送り、意図を共有することで事故のリスクを軽減することもできます。
また、危険物が落下したり崩れたりする場合に備え、事前に作業員全員でシミュレーションを行うことも必要です。
道に壁倒壊、女子高生下敷きになり死亡 岐阜市の工場解体現場

岐阜市の解体工事現場で外壁が倒れ、通行中の女子高校生が死亡した事故から14日で1カ月を迎える。ある解体業関係者は「起こるべくして起きた」と話す。解体業界では、価格競争の末に安全性が犠牲になることが横行しているという。法のチェックを受けず、安全に必要な経費を減らした危険な現場は各地にあると指摘している。
事故は、ステンレス工場の解体作業中、高さ約11メートルの外壁が長さ約18メートルにわたって突然倒れた。自転車で通りかかった岐阜県大垣市の高校2年川瀬友可里さん(17)が、その下敷きとなった。
県警によると、作業をした業者は、外壁が倒れないようにワイヤで支えたり、歩道に警備員を配置したりする安全策をしていなかった。また、鉄骨の解体に必要な資格者を現場に置かず、倒壊防止策を含む作業手順を定めた計画書も作っていなかったという。
こちらは2010年10月に発生した事故。工事現場の前を通りかかった高校生が外壁の下敷きになってしまった事例です。
この事件では、解体業者側の「安全対策の不十分さ」が指摘されています。
警察の調査によると「ワイヤーによる外壁の固定がされていなかった」「資格者や警備員を現場に置かずに作業をしていた」ということが判明したそうです。
このように、一部の解体業者ではコスト削減のために安全対策を怠っている企業が存在します。
解体業者には法で定められた安全管理講習会に参加したり、倒壊防止策を練る義務もあるため、依頼側としても事前に企業の取り組みや体制を確認することが必要です。
工事現場、パネル倒れ男性死亡 東京・日本橋、下敷きに

21日午前11時ごろ、東京都中央区日本橋人形町2のビル工事現場で、工事用のパネルが倒れたと119番があった。東京消防庁によると、通行人とみられる50?60代くらいの男性が倒れたパネルの下敷きになり、病院に運ばれたが死亡が確認された。
現場は東京メトロ人形町駅から北東へ約200メートルのオフィス街。
こちらは2014年8月に発生した事故です。
解体工事の際、粉塵の飛散や防音のために、こうしたパネルを現場の外側に設置することは多くあります。今回の事故について施工業者は「パネル養生の支柱を抜きすぎてしまった」と話しており、パネルの強度が弱くなっていたことが原因と見られています。
解体業者による事故防止の取り組み

このような事故の発生にあたって、解体工事の施工業者も安全対策を強化しています。
では、具体的にどのような対策を行っているのか見ていきましょう。
KY(危険予知)活動
KY活動とは「危険予知活動」の略称で、事故や災害を未然に防ぐために事前に危険を予想し、指摘しあう訓練活動のことをいいます。ほかに、「ツールボックスミーティング」とも呼ばれています。
KY活動は、次の4つの項目によって構成されています。
現状把握
作業内容にどのような危険が潜んでいるか、作業員同士で問題点を指摘しあう訓練です。
各々で問題点の指摘を自由に行い、それぞれの指摘内容の批判は避けるようにします。
例えば、その日の作業内容がユンボでの解体作業だったとします。「作業員がつまづいて転倒し、重機にぶつかり怪我をしてしまう」「誘導者がいないので、走行中に周囲の物や作業員にぶつかってしまう」などを作業員が指摘し、意見を出し合います。
本質追求
指摘内容が一通り出揃ったら、「どうしてそのような事故が起こってしまうのか」の原因追求をします。
例えば先ほどの例で言えば、「重機の周辺に作業員が配置されていたからではないか」「誘導者がおらず、操縦者が周囲の状況について把握できていなかったのではないか」など、作業員同士で検討し、問題点を整理するのです。
対策樹立
問題点を整理したら、作業員同士で改善策・解決策を挙げていきます。
「重機の稼働中、作業員はその周辺に近づかないようにする」「重機の誘導者を決め、稼働中の指示を出させる」など、各々で思いついた解決策を発表していきます。
目標設定
挙がった改善策・解決策を討論しあい、作業員全員の合意の上、全体目標を設定します。
活動の報告書をまとめ、作業員全員で呼称して、共有しながら実際の作業を行います。
立ち入り禁止措置

作業中の現場には、作業員等の関係者以外が立ち入ることができないよう、立ち入り禁止措置を施します。
また、重機を使用している際など、倒壊や落下のおそれがある場所には余裕をもって立ち入り禁止措置を行い、一般の方々が現場に近づけないようにするのです。
火気安全対策
ガスボンベ等の撤去作業ではもちろんのこと、例えば外壁補修等で使用する塗料にも、発火の危険性はあります。
そうした火災の原因となり得る要素の管理を安全に行うため、火気を使用するエリアを定め、エリアの責任者を定めて共有することが重要です。
安全パトロール
付近に一般の方がいないか、パネルは固定されているか、倒壊や落下の危険性があるものがないかを定期的に確認する巡視者を配置し、安全管理の点検・安全の確保を行います。
5S活動

5Sとは、整理、整頓、清掃、清潔、躾の頭文字をとった言葉で、5Sに基づいた業務管理を5S管理、5S活動と呼びます。
いらないものは処分する
使用したあとは決められた場所に物を戻し、いつでも取り出せるようにする
掃除を常に行い、現場の清潔な状態を守る
整理・整頓・清掃を維持する
決められたルールや手順を守り、正しい習慣をつける
5S活動による効果としては、職場環境の美化や作業員のモラル向上が期待されます。
ひとつひとつの作業をずさんにせず丁寧に行うことで、業務の効率化・不具合流出の未然防止を目指し、現場の安全性を向上させているのです。
行政による事故防止の取り組み

各業者の安全対策についてご紹介いたしましたが、国や自治体でも、解体工事での事故を防ぐための取り組みは行われています。
行政ごとの指導
国土交通省による「公衆災害防止対策」においても、解体工事にあたって外壁等の崩落などによる事故を防止することが義務付けられています。
更に、解体工事を行う地域の自治体によって指導基準が設けられていて、その地域で解体工事を行う業者は、指導基準を守った安全な工事を行わなくてはなりません。
遵守事項
例として、東京都武蔵野市の指導基準の遵守事項をご紹介します
2.粉塵対策として、散水を徹底して行う
3.建築物等の周辺には、仮囲い・養生シートなどを設置する
4.建築物等の敷地境界で、規制基準を超える騒音が発生し得る場合には、防音パ
ネルやそのほかの防音措置等の設置をする
5.工事に使用する機器を、本来の用途以外には使用せず、コンクリート片の小割
りやバケットによるふるい等は、必要最低限に留める
6.解体工事等の現場には責任者を定め、安全管理を徹底して行う
7.解体工事等のための車両の出入りには、一般の通行人の安全確保のために、的
確な誘導を行う
8.重機のアイドリングストップを励行する
9.解体工事棟を行う建築物等に、人体や環境に有害とされる物質がある場合に
は、法令等に則った適正な処理を行う
10.解体工事現場には、施工業者の名前と連絡先を、工事期間中必ず掲載する
11.解体工事等は日曜日・祝日を休業として、施工期間が1ヶ月を超える場合
は、土曜日の施工について騒音・振動を低減できるような工程管理を行う
12.建築物等の状況から、ねずみなどの害獣・害虫の生息が予測できた場合、発
生状況の調査と、必要に応じて駆除対策を行う
引用:建築物の解体工事等における指導の基準について | 武蔵野市
参考 建築物の解体工事等における指導の基準について|武蔵野市公式ホームページ武蔵野市公式ホームページ工事の周知
引き続き武蔵野市の指導基準を例として、ご紹介致します。
解体工事を行う際、近隣住民の方々や通行人の方々に工事を行うこと・行っていることを把握してもらうために、工事の周知を徹底しなければなりません。
周知範囲は工事を行う敷地の境界線から、工事を行う建築物等の高さの2倍にあたる水平距離の範囲とされています。つまり、高さ7mの建築物を解体する場合だと、建築物のある敷地の境界線から、14m先までがその範囲内となります。
工事の周知のために記す事項は、次のとおりです。
除去方法
引用:建築物の解体工事等における指導の基準について | 武蔵野市
参考 建築物の解体工事等における指導の基準について|武蔵野市公式ホームページ武蔵野市公式ホームページ労働安全衛生法

労働安全衛生法(通称労安衛法)とは労働者の安全と衛生について定めた法律のことをいい、解体工事においては作業員の安全と衛生環境の維持のために定められています。
(1)安全衛生管理体制
一定規模以上の事業場においては、安全衛生業務全般を統括する責任者を選任しなくてはなりません。
さらに、一定の業種で労働者が100人以上使用する現場では「安全委員会」を、50人以上の使用する現場では「衛生委員会」を設置することが義務付けられています。
こうすることで、作業員が危険な環境・健康管理上問題のある環境で働かなくてはいけない自体を防げ、解体現場における事故で最も多かった「作業員が被害者となる事故」を防ぐことができます。
(2)労働者の危険又は健康障害を防止するための措置
労安衛法第4章において、事業者は様々な労働災害防止措置を講ずることが義務付けられています。ただし、事業によって具体的な措置は異なるため、大部分は厚生労働省令に委ねられています。
(3)機械等並びに危険物および有害物に関する規制
機械の規制に関しては、特に危険を伴う作業を行う場合、その機械の製造に労働基準局長の許可が必要であり、作業員に危害を及ぼすような可能性のある機械に対しては、譲渡・貸与に制限がかけられます。
有害物の規制に関しては、取り扱いの過程において作業員に重大な健康被害を及ぼす物質に対しては、製造・輸入・譲渡・提供・使用が禁止されています。
例えば解体工事の際に作業員に被害を及ぼし、現在では建築の際の使用も制限されているアスベストなどは、より細かく取り扱いについて制限が課せられています。
(4)労働者の就業に当っての措置
労働災害の帽子のため、事業者が設備や作業環境等について安全を図るとともに、作業員自信がその業務に含まれる危険性や有害性を把握し、適切な対応方法をしっかりと理解した上で、作業に臨むことが義務付けられています。
そこで、事業者は作業員を雇い入れた際、機械や危険物質等の危険性・有害性・取り扱い方法などの安全衛生教育を必ず行わなくてはなりません。
(5)健康の保持増進のための措置
労安衛法では、作業員に対して医師による健康診断を実施することを義務付けています。
また、平成17年の法改正によって長時間の労働者へは医師による面接指導を実施することも義務付けられました。週40時間を超える労働がひと月あたり100時間を超え、疲労の蓄積が見られる労働者が申し出た際は、事業者は労働者に医師による面接指導を受けさせなくてはならない、ということです。
(6)事業者及び労働者の義務
安全衛生法の様々な措置について、中心的な責任を負うのは事業者です。
事業者が労安衛法に違反すれば、懲役や罰金などの罰が科せられることになります。
現場の安全を確保するためには、実際に作業する作業員自信の自覚・協力も不可欠ですから、労安衛法の必要事項の遵守を、作業員一人一人にも理解し、協力してもらうことが重要となっています。
参考 労働安全衛生法 | e-Gov法令検索労働安全衛生法 | e-Gov法令検索まとめ
いかがでしたでしょうか。今回は、解体工事現場の事故事例と、それを踏まえた事故対策についてご紹介いたしました。
大きなものを壊したり、運びだしたりする解体工事。作業員のみならず、近隣に住む方々や、周辺を通行する方々が被害に遭った事例は少なくありません。
しかし、だからといって「解体工事は元々危険な作業なのだから、仕方ない」と諦めてはなりません。時代が進むとともに、解体工事も安全で安心な工事ヘと成長していかなくてはなりませんね。
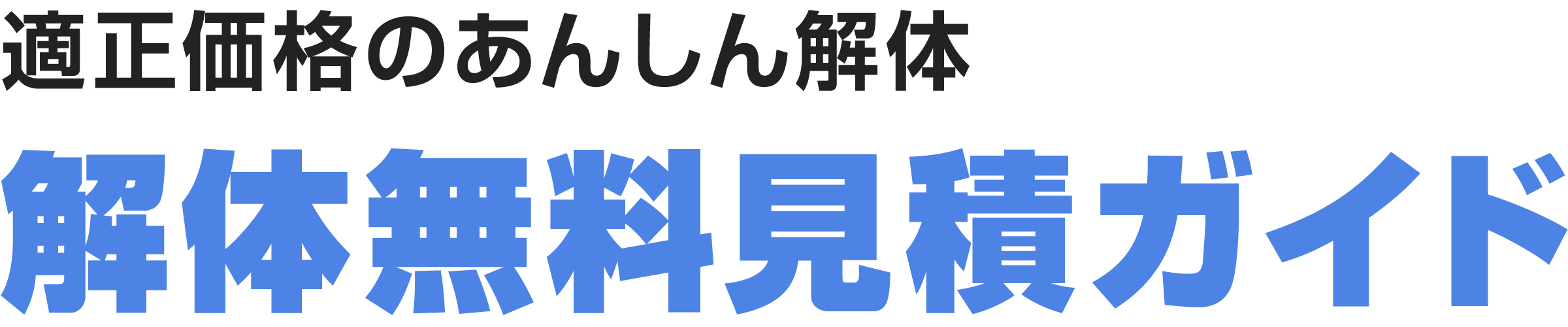

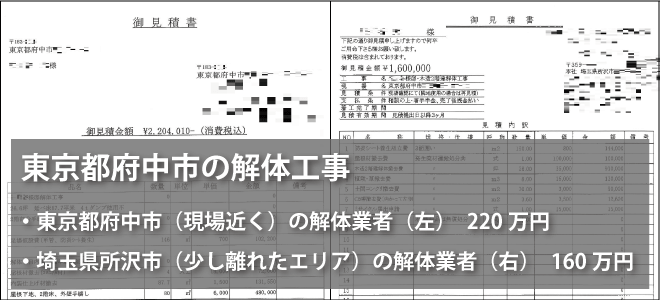
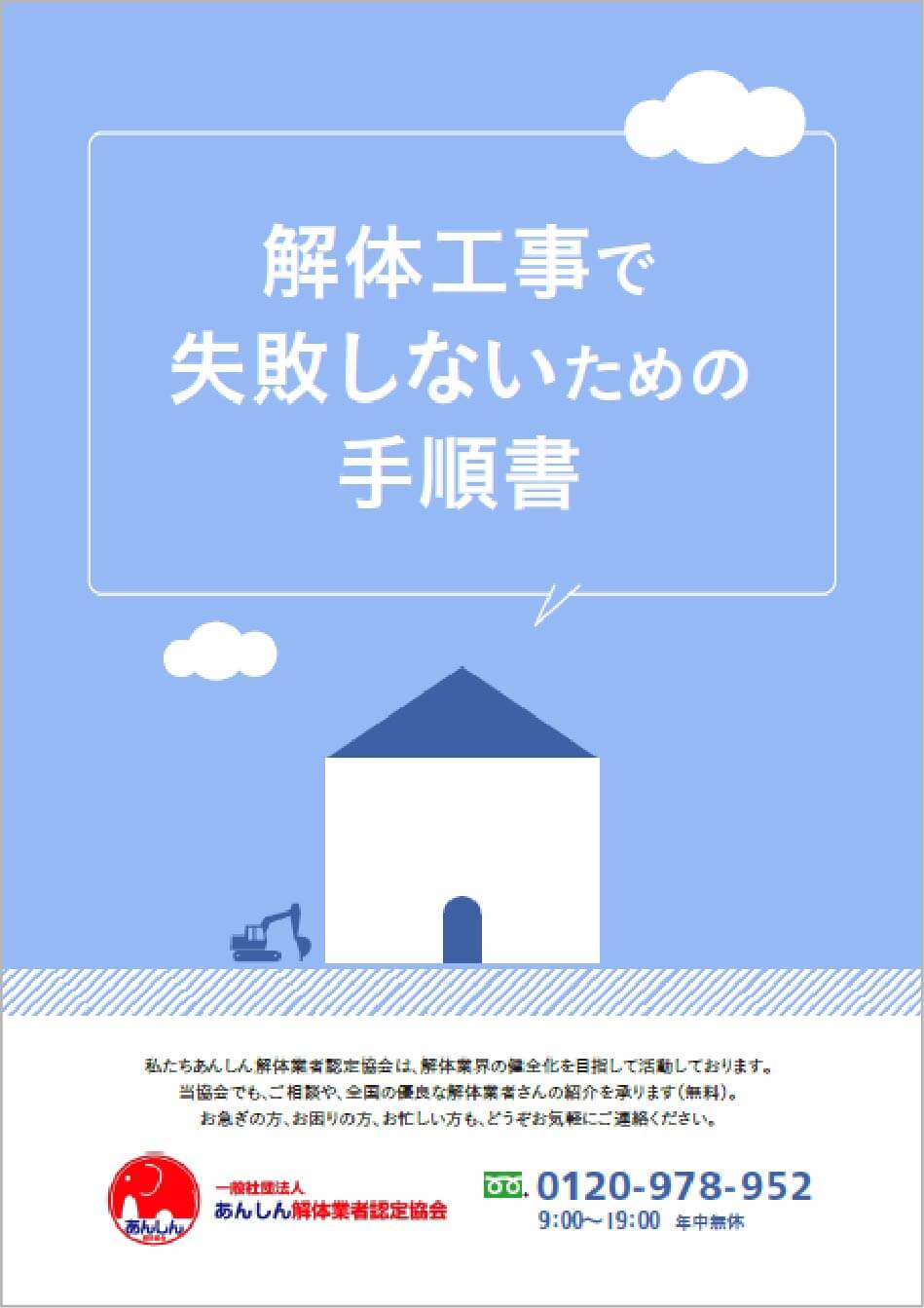


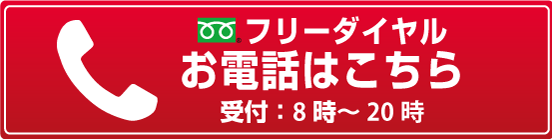
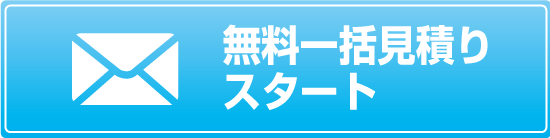
コメントを残す