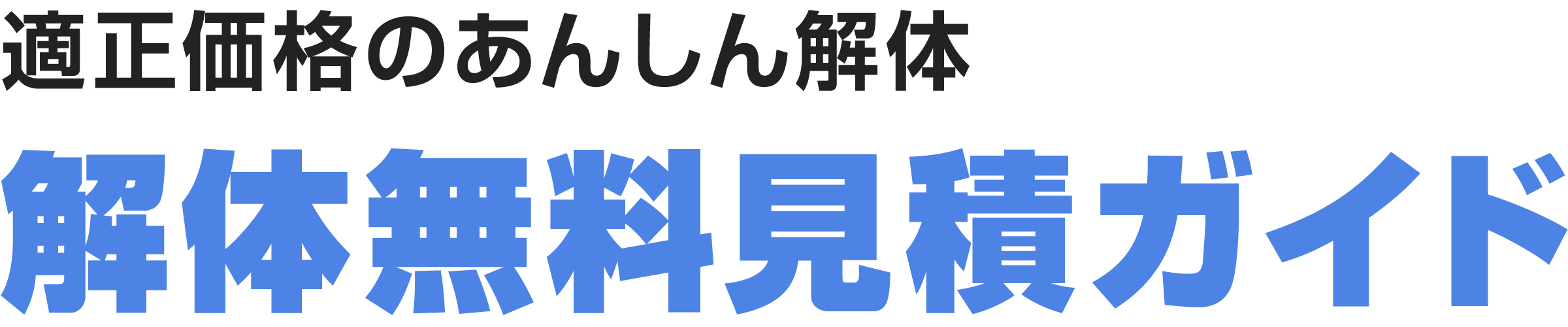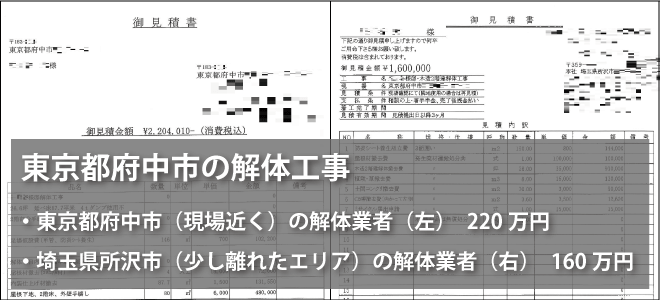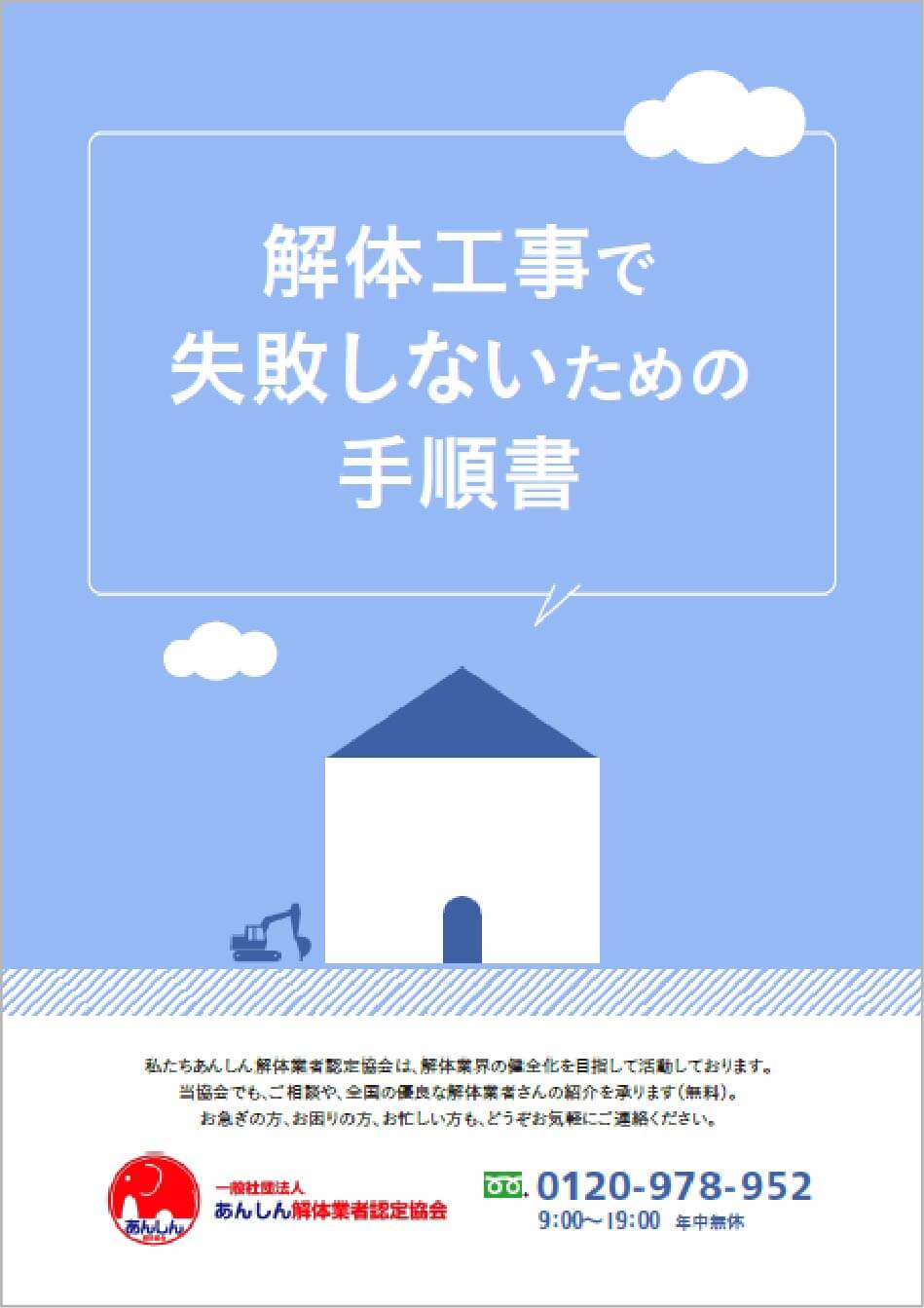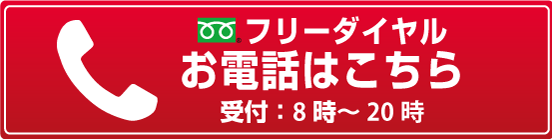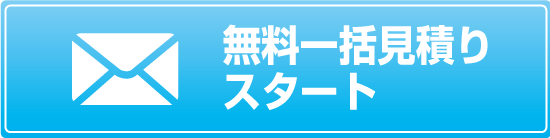家の撤去工事をするときは、広さや構造に応じた届出が必要です。届出は大きく分けて6種類あり、各自治体の窓口などに提出します。また、届出によっては法律で締め切りが決まっていて、破った場合は罰金などが科されるので注意が必要です。
締め切りが不安な場合は撤去業者への代行を検討しましょう。なお、ほとんどの届出は撤去業者が代行できますが、中には自分で手続きをすることで費用を大幅に節約できるものもあります。撤去工事に伴う届出の内訳や注意点など、この記事を参考にして撤去工事の準備にお役立てください。
必要な届出の内訳と詳細
撤去工事で必要な届け出の内訳と詳細は以下の通りです。
| 必要な届出・申請 | 期限 | 申請の義務 | 第三者へ委任 | 委任した場合の費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1.アスベスト除去の届出 | 工事着手の14日前 | 施主/撤去工事事業者 | 可能 | 他の申請と合わせて 約3~5万円 |
| 2.ライフラインの停止 | 工事着手の前日まで | 施主 | 不可 | – |
| 3.建設リサイクル法 に関する届出 |
工事着手の7日前 | 施主 | 可能 | 他の申請と合わせて 約3~5万円 |
| 4.道路の使用許可申請 | 工事着手の前日まで | 撤去工事事業者 | 不要 | 他の申請と合わせて 約3~5万円 |
| 5.建築物除去届 | 工事着手の前日まで | 施主 | 可能 | 他の申請と合わせて 約3~5万円 |
| 6.建物滅失登記申請 | 工事完了後1か月以内 | 施主 | 可能 | 約3~7万円 |
建物の撤去工事にあたり、最低限必要な届出は上記の6種類です。ライフラインの停止以外は撤去業者や第三者へ委任することができます。届出を撤去業者に依頼する際は委任状の記入を忘れないようにしましょう。「建物滅失登記」については第三者(土地家屋調査士)に委任した場合に3万円~7万円の費用が必要となるため、費用を節約したい方は自分で滅失登記を行うようにしましょう。
届け出ごとに詳しく解説
撤去工事に必要な届出はそれぞれ出すべき時期や場所が異なります。
それぞれの届け出を順番に見ていきましょう。
1.アスベスト除去の届出
撤去する建物にアスベストが含まれている場合は除去作業の届け出が必要になります。
アスベストの種類によっては届け出が不要な場合がありますがご自身で判断するのは難しいです。撤去業者さんに撤去工事の見積りを依頼して事前に調査してもらってください。
ただし、アスベストは使用されている場所によっては確認するのが難しいため、事前に把握できず、撤去工事の途中でアスベストが発見されてしまうケースもあります。見積りに来た業者さんだけで判断ができない場合は専門の機関にアスベストの調査を依頼しましょう。
なお、アスベストについてご存知ない方は以下の記事も参考にしてください。
 解体工事の前に知っておくべきアスベストの危険性と処理方法
解体工事の前に知っておくべきアスベストの危険性と処理方法
アスベストの除去に必要な届け出は「特定粉じん排出等作業実施届」です。
作業の14日前までに各都道府県の定める窓口へ届け出ます。
ご自身でも出来ますが、撤去工事業者さんでも代行ができるので追加費用(他の申請と合わせて約3~5万円)が気にならない方は撤去工事と合わせて業者さんにお願いされるのがおすすめです。
もし、届け出を怠ると、3ヶ月以下の懲役、もしくは30万円以下の罰金が科せられるのでアスベストが含まれていた場合はご注意ください。
2.ライフラインの停止

撤去工事の前には事前にライフラインを停止、もしくは撤去しておかなければなりません。
一般的なライフラインといえば電気、ガス、水道、その他にも電話、インターネット、ケーブルテレビなどの通信網もライフラインに含まれます。
いずれのライフラインも電話一本で簡単に停止できます。ライフラインによっては停止まで2週間前後かかる場合や、撤去費用が発生することがあるので早めに連絡しておきましょう。
なお、撤去工事のホコリを抑える散水に使用するので水道だけは停止させないよう注意してください。
3.建設リサイクル法に関する届出
各地域の自治体は法律に沿って建物の廃材が正しく処分されたかどうかをチェックし、取り締まっています。
そのため、建物の種類と、発生する廃材の見込み量を事前に届け出なければななりません。
対象になるのは延床面積の合計が80㎡以上(約24坪)で木材や鉄、アスファルトなど特定の建材が使われている建物です。
- 床面積の合計が80㎡以上
- 特定建設資材(木材や鉄、アスファルトなど)が使用されている
一般的な木造2階建ては30坪以上あります。なので基本的に撤去工事をする場合は届け出の対象だと考えてください。
届け出の期限は撤去工事に着工する7日前です。なお、届け出を怠ると罰金が科せられます。金額は建物の構造により細かく決められているので以下のリンクを参照してください。
とはいえ、建設リサイクル法の届け出が必須なのは撤去工事業者さんも把握しています。なので、届け出を業者さんに代行してもらうのが一般的です。業者さんの中には無料で届け出の代行を引き受けてくれる場合もあるので見積りの際に確認してみましょう。
届け出を撤去工事業者さんに代行してもらう場合は届け出を「委任」したに過ぎません。基本的には問題ありませんが、業者の違反を知っていて黙認した場合は罰金の対象になる可能性があります。業者さんを選ぶ際はご注意下さい。
届け出に必要な書類の一覧
| 書類 | 内容 |
|---|---|
| 届出書 | 発注者の氏名や工事の概要を記入します。 |
| 分別解体等の計画等 | 建物の構造や周辺状況、工程に応じた作業内容を細かく記入します。 |
| 工程表 | 対象となる撤去工事計画の工程表です。 |
| 設計図または写真 | 撤去工事の場合は、外観写真を添付し、必要に応じて図面を添付します。 |
| 案内図 | 工事する建物の場所を、住宅地図の複写に着色し明らかにします。 |
| 委任状 | 申請者(施主)の代理として届出を行うときに必要です。 |
詳しくは各自治体の窓口でお問い合わせください。
なお、申請書は各自治体のホームページから簡単にダウンロード可能なので気になる方は確認してみて下さい。
4.道路の使用許可申請

撤去工事が交通の妨げになってしまうような場合は、道路の使用許可が必要です。
撤去工事の際の道路の使用許可は、本来撤去工事を請け負った業者が申請するよう定められていますが、一般的には申請費用を加算して撤去工事業者が請け負います。
もちろん、直接依頼主が警察署に行って道路の使用許可を取る事もできます。
ちなみに道路の使用許可を取るには、管轄の警察署に行って「道路使用許可申請書」と「添付資料」を提出して、手数料を納めます。
道路の使用許可申請に必要なものは以下のとおりです。
- 道路許可申請書 (各警察署により様式が異なります)
- 添付資料 (撤去工事現場周辺の地図等)
- 手数料 2,000~2,700円
道路の使用許可を自分でとると、その分費用を安くしてくれる撤去工事業者もあるため、確認してみましょう。なお、道路使用許可が必要なのに使用許可をとらなかった場合は3ヵ月以下の懲役または5万円以下の罰金が科せられます。
5.建築物除去届
建築基準法第15条で、工事施工者が建築物を除却しようとする場合、都道府県知事に届出をする必要があります。(※ただし、建築物又は工事部分の床面積が10平方メートル以内の場合、または建替えに伴う除去工事の場合には必要ありません。)
建築物除却届は、除却工事施工者が工事前日までに行います。
届出は委任状をもって、撤去工事業者への委任もできます。
委任した場合は他の届出の申請なども含め、3~5万円程かかるのが一般的です。
6.建物滅失登記申請
最後に、撤去工事が完了して「建物が無くなった」ことを申請するために、滅失登記申請を法務局に届出ます。
滅失登記申請はやや専門的な知識が必要です。そのため不動産の表示に関する登記の専門家である「土地家屋調査士」に委任する方法があります。その場合3万円から7万円ほどの手数料がかかります。
なお滅失登記を個人で済ますと、かかる費用は登記簿謄本の取得費用(1通600円)のみです。
建物滅失登記申請は、撤去工事後1ヶ月以内に申請する必要があり、申請を怠ると10万円以下の過料になります。
必要な書類は以下の通りです。
- 登記申請書
- 取毀し証明書
- 撤去工事業者の印鑑証明書
- 撤去工事業者の資格証明書もしくは会社謄本
- 住宅地図
- 登記申請書のコピー
滅失登記申請を代行してもらう場合は以下の2点も必要です。
- 委任状(自分でやる場合は必要ない)
- 依頼人の印鑑証明(自分でやる場合は必要ない)
なお、登記申請書は法務局のホームページからダウンロードできます。
滅失登記申請書の記入例はこちらです。
https://blog.kaitai-guide.net/blog/wp-content/uploads/2017/03/touki2.pdf
滅失登記申請書の記入や必要書類を集めるには撤去工事業者の方たちの協力も必要なのでもし自分で申請して費用を抑えたい場合は、撤去工事の見積りの時点で業者の方に確認して下さい。
大半の届出は代行してもらえる? 自分でやるべきなのは1種類のみ

6種類の届出を知ると、「手続きが大変そうだな…」と思ってしまうかもしれません。
ですが、安心してください。
実は、自分で行う届出は6種類のうち建物滅失登記だけだからです。
本来の届出義務者は発注者であるお施主様ですが、優良な撤去工事業者なら委任状を渡して代行してもらえるケースがほとんどだからです。(手数料がかかる場合は、見積書に官公庁届出として記載されます)
ただし、水道に関しては建物の撤去工事中に使うことがありますので、業者さんと相談しましょう。
近隣挨拶も忘れずに
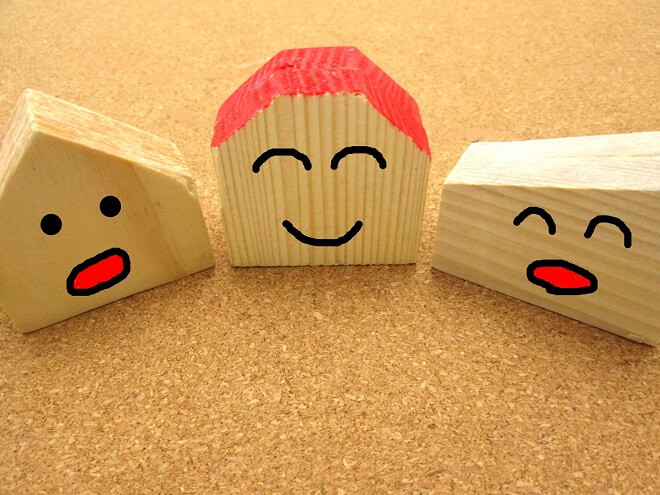
届出とは別に、建物の撤去工事前に必ずやって頂きたいのが現場周辺の近隣挨拶です。
撤去工事で生じる粉じん、ホコリ、騒音、振動などはいくら周囲をシートで囲っても防ぎきることはできません。
事前に挨拶に行かなかった事が原因でささいな事に言いがかりをつけられてトラブルに発展してしまう事があります。
近隣の方とのトラブルを未然に防ぐためにも撤去工事現場周辺の近隣挨拶は最も重要と言えます。
参考 取り壊し工事に伴う隣家の補修費用は誰の負担?トラブルの種類と回避方法解体工事の情報館
解体工事の届出についてのまとめ
撤去工事の届出をするにも、アスベストの有無によって必要な届出の準備も撤去工事の費用も変わってくるので、撤去工事を計画するのであれば真っ先にアスベストの有無を調査する事をおすすめします。
また、撤去工事業者の中には撤去工事の見積もりの段階で、アスベストの有無を確認できる業者もあります。