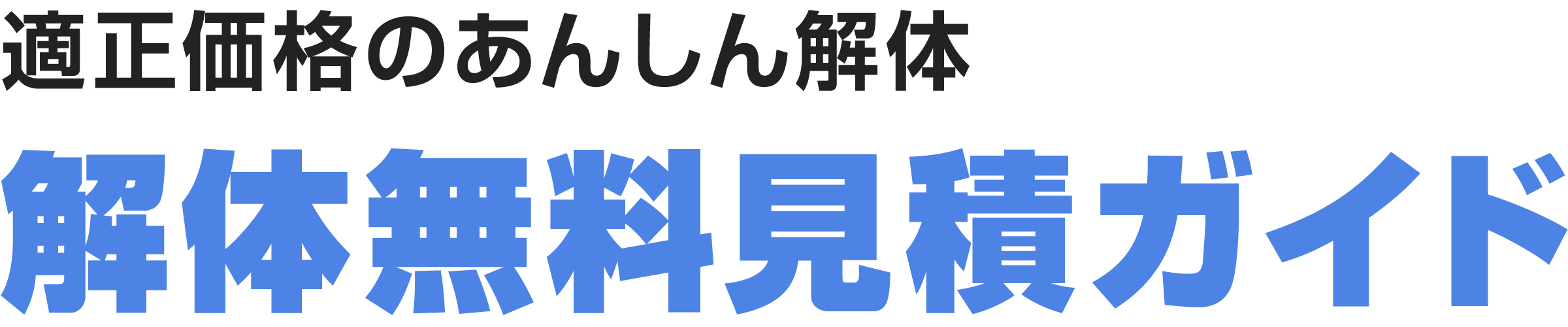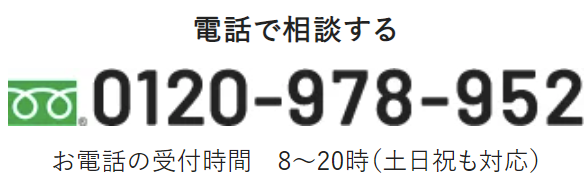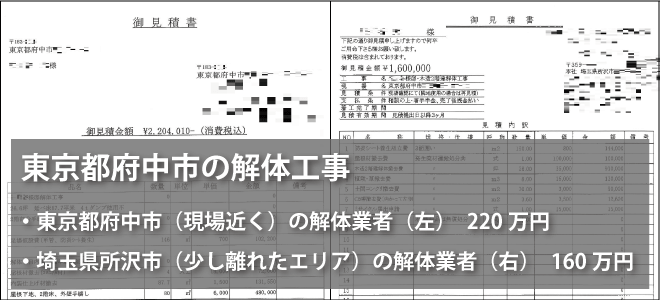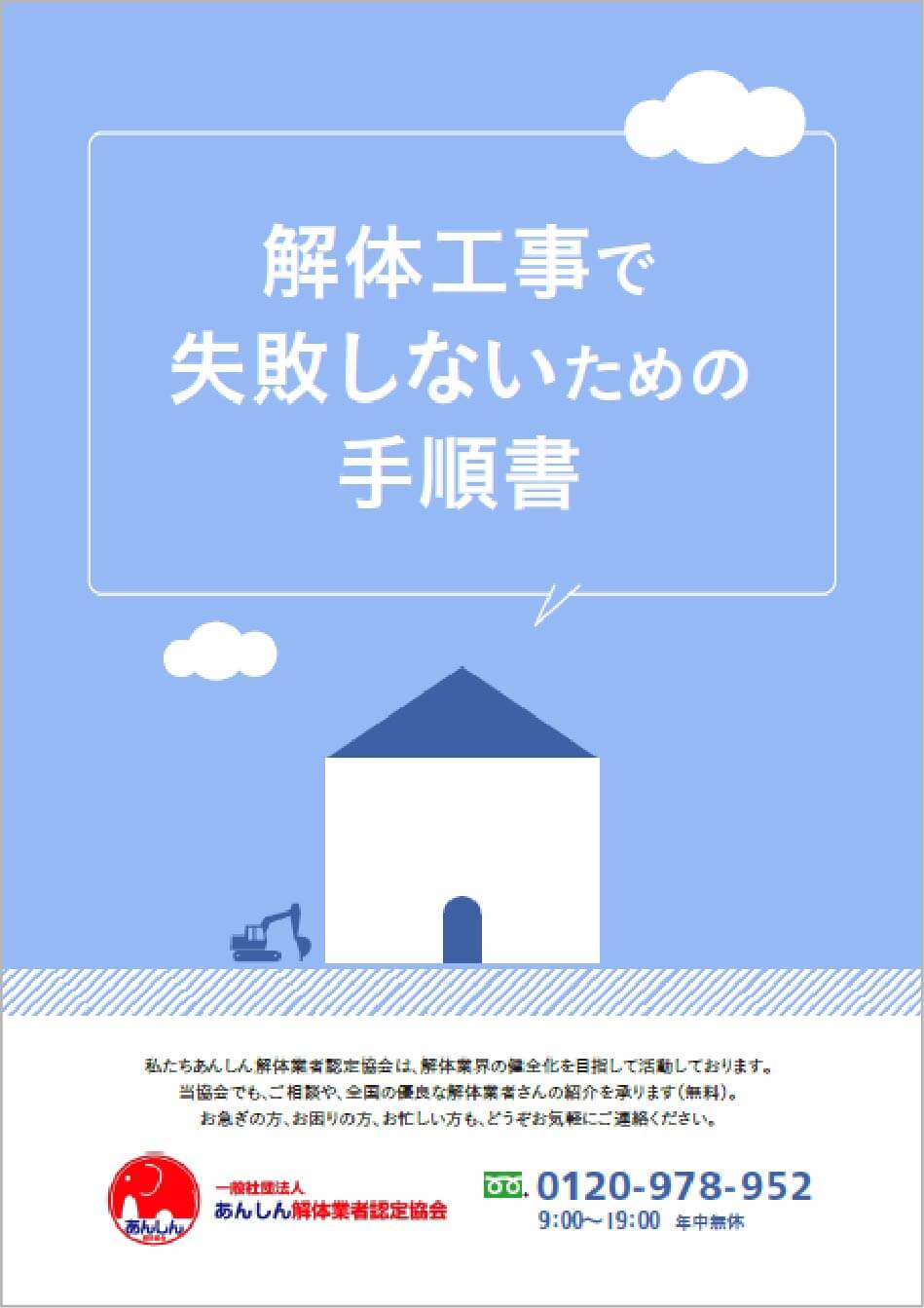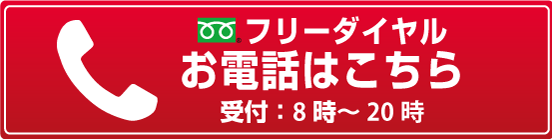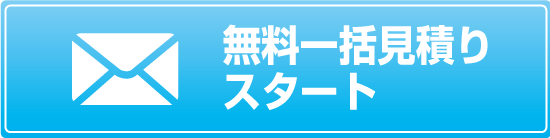せっかく火災保険に入っているのにわざわざ自費でお家の修理をしてしまう人がいます。確かに保険の申請手続きは面倒ですし、保険を使って修理すると保険料が上がってしまうんじゃないかと不安に感じてしまう気持ちは分かります(火災保険の給付を事由には保険料は上がりません)。
だからといって、火災保険を掛け捨てにしてしまうのはもったいないです。この記事を読んだ方にはぜひ、火災保険を正しく利用して大事なお家をしっかり直してほしいと思います。
意外と知らない火災保険の適用範囲
火災保険の対象は火災だけだと思われがちですが、実際、補償内容によっては自然災害も含まれている場合があります。例えば風水害、積雪、落雷など多くの自然災害が補償の対象になっているケースがほとんどです。もし、地震以外の災害で被災された場合は積極的に火災保険の申請を検討しましょう。
火災、風災、水災、雪災、落雷、破裂、爆発、ひょう災、水濡れ、盗難、破損、汚損など
- 地震による建物の破損、倒壊
- 地震により発生した火災の被害
特に注目したいのは台風や豪雨による災害でも火災保険の対象になる点です。そこで、火災保険を利用した場合、具体的にどのような災害に対していくら位の保険料が下りるのか実例をもとに見ていきましょう。
2018年関西地方に上陸した台風21号の例

| 保険金額の目安 | 約80~約300万円 |
|---|
2018年の台風21号は68棟の建物を全壊、833棟もの建物を半壊にしました。なお、火災保険や車両保険など、翌年の2019年3月までに合計で1兆600億円以上が支払われました。
建物の被害状況は建物が破損した割合によって決まります。なお、建物の被害状況は罹災証明に記載され、保険金の申請で必要です。建物の被害状況によってもらえる保険金額は異なりますので罹災証明を発行してもらう際は確認漏れがないよう、慎重に調査をしてもらいましょう。
- 全壊…….50%以上
- 半壊…….40%以上50%未満
- 一部破損…20%以上40%未満
参考: 内閣府防災情報のページ
2018年の台風21号の影響で被害に遭った建物は以下のとおりです。
| 建物の被害 | 棟数 |
|---|---|
| 全壊 | 68棟 |
| 半壊 | 833棟 |
| 一部破損 | 9万7009棟 |
| 床上浸水 | 244棟 |
| 床下浸水 | 463棟 |
2018年1月に発生した大雪の例

| 保険金額の目安 | 約80~約150万円 |
|---|
2018年1月中旬から2月上旬にかけて、日本海側を中心に何度も大雪が観測されました。大雪では積雪の重みでカーポートが倒れたり、滑り雪で雨樋(あまどい)が歪んでしまうケースがあります。ただ、いずれも火災保険の対象です。被害を確認したら漏れなく申請してください。
2019年関東地方に上陸した台風15号・19号の例

2019年の台風15・19号は複数の河川で氾濫、決壊をおこし大きな被害を出しました。前年の台風21号に比べて被害は圧倒的に大きく、支払われた火災保険も高額です。
| 保険金額の目安 | 約100~400万円 |
|---|
2019年の台風15号・19号の影響で被害に遭った建物は以下のとおりです。
| 建物の被害 | 棟数 |
|---|---|
| 全壊 | 3,202棟 |
| 半壊 | 2万7,154棟 |
| 一部破損 | 3万25棟 |
| 床上浸水 | 7,331棟 |
| 床下浸水 | 2万1,774棟 |
保険金申請の具体的な手順
保険金の申請では災害で壊れた部分を正確に把握したり、仮に修理した場合に必要な見積りを作成したり、実際に保険会社に問い合わせるまでにいくつか手順を踏む必要があります。そのため、手順を複雑に感じて申請そのものを先延ばしにしてしまう方が少なくありません。
もちろん、保険会社はなるべく保険金の申請がないほうが利益を出せるので、申請のタイミングや申請方法を積極的に教えてくれることはありません。その結果、本来なら補償の対象になるのに申請されず放置されている被害がたくさんあるのです。
でも、安心してください。保険金の申請は損害箇所さえ正確に把握できれば、残りの手順はそれほど難しくありません。また、損害箇所の調査も専門の調査会社に依頼すれば驚くほどスムーズに保険金の申請が可能です。それでは、申請に必要な手順を詳しく見ていきましょう。
保険金申請の具体的な手順
【ステップ1】専門業者に損害箇所の調査を依頼
【ステップ2】保険会社に保険申請をする
【ステップ3】保険金額の決定と受け取り
【ステップ1】専門業者に損害箇所の調査を依頼
火災保険金の申請にあたってまず最初にやって欲しいのは損害箇所の調査です。保険の対象を明確にしてどの程度の金額が申請できるのかを把握します。なお、調査は専門の調査機関を使って漏れなく該当する部分を調べてください。抜けや漏れがある状態で申請をしてしまうと正規の保険金額を受け取れません。
かといって申請手続きを先延ばしにしていると火災保険の申請目安である3年を過ぎてしまい、保険の適用が受けられなくなる恐れがあります。
調査機関にはどんなところが?
損害箇所の調査をする専門の調査会社はたくさんあります。基本的にどの業者に依頼しても問題ありません。ただし、保険の申請をしても必ず保険金が下りるわけではないので、依頼する調査会社は保険金が下りなかった場合、費用が発生しないところを選ぶようにしましょう。以下の表は保険金が下りなかった場合には調査費が無料になる調査会社の例です。
| 調査機関名 | 問い合わせURL |
|---|---|
| 一般社団法人 全国建物損害調査協会 | |
| 株式会社ONE’S BEST | |
| 株式会社 橘フォーサイトグループ |
専門の調査会社に損害箇所の調査を依頼すると損害箇所を調査した証明と、修理した時に発生する費用の見積りを作ってくれます。基本的には、その後の申請に必要な書類のチェックまでを行ってくれるのが一般的ですが、念の為、調査を依頼する際にどこまでサポートしてくれるのか確認しておくと安心です。
調査を依頼するなら結局どこ?
なお、おすすめの調査機関は全国建物損害調査協会です。同協会には損害登録鑑定人や二級建築士といった有資格者が在籍していることもあり、調査した家屋は累計10,000件以上と豊富な実績があります。もちろん、万がいち保険金が下りなかった時は調査費が発生しません。ぜひ、お気軽にご相談ください。
【ステップ2】保険会社に保険申請をする
実際にあなたが行うのは保険会社への保険申請です。申請と言っても保険会社へ事故の連絡をして、調査会社に作成してもらった見積書類を保険会社に送付するだけです。
保険会社への問い合わせは慎重に
何か不安があれば真っ先に問い合わせたくなるのは加入している保険会社です。でも、保険会社に電話で問い合わせる場合は少し注意が必要です。保険会社は問い合わせの内容を全て録音しており、受け答えの内容によっては保険の申請を断られてしまうケースがあるからです。具体的には以下の点を意識して問い合わせてください。
- 分からないことは分からないとはっきり答える
- 虚偽の内容は絶対に申告しない
- 自分自身で損害の箇所を確認してから(調査会社に調査をしてもらったとしても必ず自分で損害箇所を確認してから問い合わせる)
保険会社を非難するつもりはないですが、保険会社の中には申請者が不利になるように会話を誘導するケースもあるようです。お問い合わせの際はご注意ください。
保険会社への正しい受け答え例
例えば、2019年の台風15号により被災して保険会社に問い合わせる場合、どのように受け答えをすればいいのか具体例をご紹介します。

保険会社

加入者

保険会社

加入者

保険会社

加入者
なお、初回の問い合わせ窓口は24時間営業の事故対応窓口につながるケースがほとんどで、問い合わせに対して上記のように端的な対応になる場合があります。
昨年や一昨年の被害について申請をする場合に「なぜ今になって申請をするのか?」といった内容を聞かれる場合がありますが、その際は「最近申請できることを知ったから」とはっきり答えれば問題ありません。
不正な申請は絶対にダメ!
保険金の受け取りで損しないよう、事前の調査や問い合わせで十分注意するのは大切です。しかし、「どうせ保険金がもらえるなら少し多めに申請しよう」などと虚偽の申請は絶対にしてはいけません。
保険の申請後は保険会社の調査が入るため、不正は必ずバレます。そうなると大きなペナルティを受けるのは避けられません。また、中には虚偽の申請を勧めてくるような業者もあります。もし、虚偽の申請を促すような業者にあっても絶対に相手せず、関わらないようにしてください。
たとえ不正な申請をしたのが業者だったとしても損をするのはあなた自身です。かならず、調査を依頼する専門業者は慎重に選んで下さい。
【ステップ3】保険金額の決定と受け取り
保険の申請後、保険会社は調査を経て保険金額を決定します。申請の内容と現状に相違がないか、また修理の見積りは妥当な金額かなどさまざまなチェックを行います。
修理費の見積りは極端に高いと却下される
保険金の申請で最も重要なのは保険会社が認めうる適正な金額を申請することです。せっかく、保険の対象になっていても、見積りが法外な金額だと保険金の支払いが大幅に減額される場合があるからです。
専門の業者以外に見積書の作成を依頼すると、自社の利益のために多めの金額を設定してしまうところもあります。修理費などの見積りは、法人登記や本所オフィス、ホームページや実績があるような専門の調査会社を利用しましよう。
手元に残った保険金はどうする?
保険会社の調査の結果、申請した金額が妥当だと認められると保険会社から通知が来て、指定口座に保険金が振り込まれます。また、保険金を受け取った方の中にはお家を修理をしてもなお、余った保険金はどうするの?といった疑問を持つ方もいます。
もちろん、余った保険金を返す必要はありません。そもそも、保険金の使いみちは加入者の自由だからです。適正な保険金を受け取ったのであれば、修理費を抑えて残りの資金を別の目的に充てても全く問題ありません。
お家の取り壊しにも火災保険が使える
万が一お家が半壊、もしくは全壊などの深刻な被害を受けてしまい、取り壊すことになった場合にも火災保険が使えます。大規模なリフォームを行うよりも建て替えた方が資産価値が上がりますし、耐震性能も新基準に対応できます。そのため、被害の状況によっては建て替えを検討される方もいます。とはいえ、建て替えにかかる費用は高額です。慎重にご検討なさってください。
解体工事は必ず相見積りを欠かさずに!
なお、解体工事のお見積りは相見積りを取るのが一般的です。複数の解体業者で見積りを比較できれば安い業者を見つけやすくなるからです。相見積りを利用して40万円以上も解体費用が安くなった事例もあります。
ちなみに、当協会が運営する『解体無料見積ガイド』では厳しい審査基準を通過した優良な解体業者の中から6社を無料でご紹介しています。決まらなかった業者へのお断りの連絡も代行していますので、是非、お気軽にお問合せください。
災害の火災保険についてのまとめ
台風や大雨、積雪などの災害も火災保険の対象です。災害によりお家が被災している方は火災保険を利用してお家の修理ができるかもしれません。ぜひ、火災保険を申請しましょう。また、火災保険の申請では損壊箇所の調査が重要です。被害を正確に特定して適正な保険金額を申請しましょう。
なお、おすすめの調査会社は全国建物損害調査協会です。これまでに10,000件以上の調査実績があり、損害登録鑑定人や二級建築士など有資格者も在籍しています。万がいち、保険金が下りなかった場合の調査費は無料です。気になる方はぜひお問い合わせください。