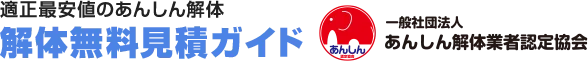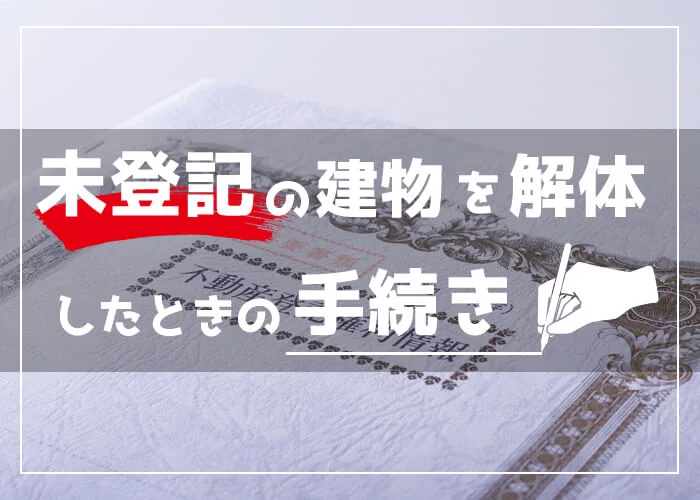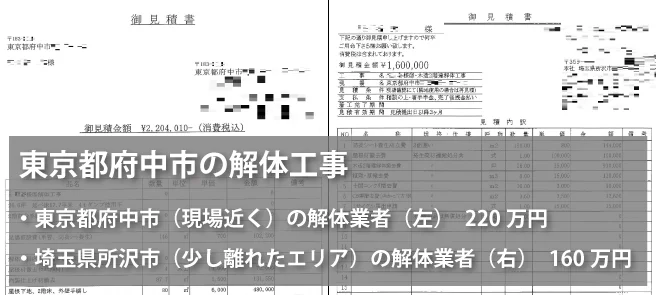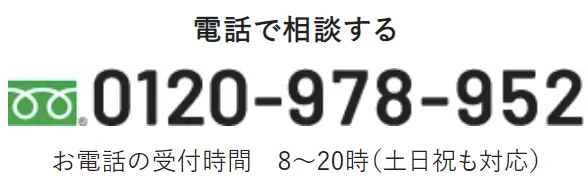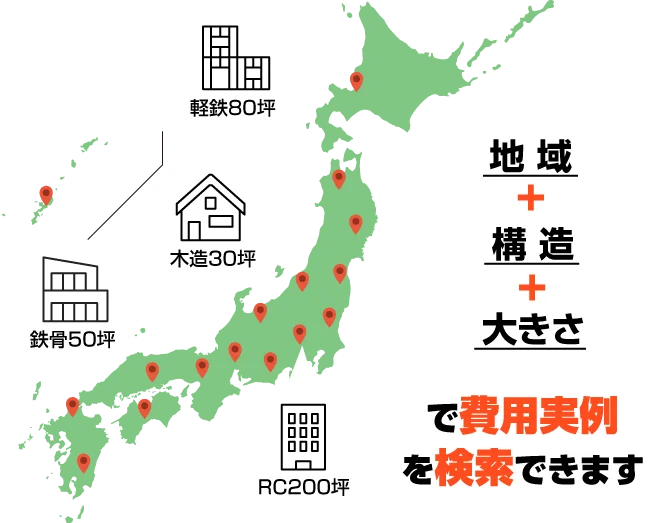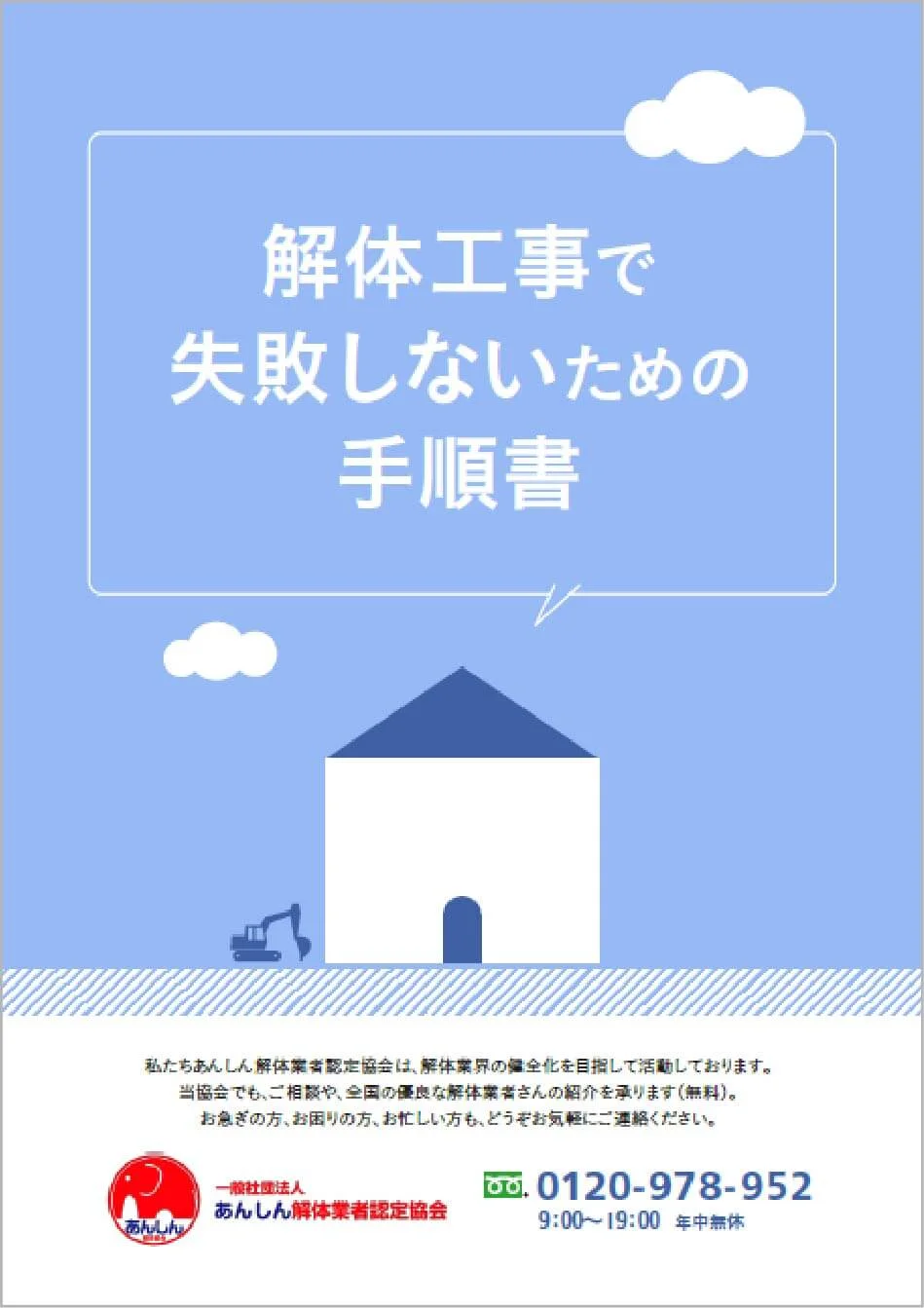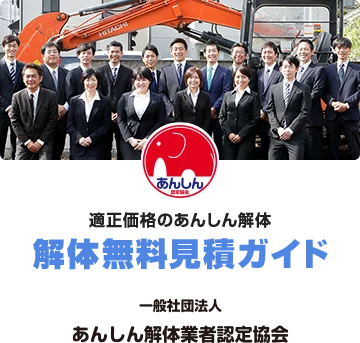未登記建物の取り壊しを行った場合、登記済みの建物とは必要な手続きや申請場所が異なるため注意が必要です。
また、未登記建物の取り壊しでは、事前に確認が必要な事項や注意すべきポイントがあります。
未登記かどうかの確認方法や、放置してしまった場合のデメリットなどもあわせて確認しておきましょう。
未登記建物とは
未登記建物とは、建物の所在や面積、所有者の情報などが登記簿に登録されていない物件のことを指します。
本来、建物を新築した時点で、建物の基本情報や権利関係を明確にするため、法務局に申請をして登記を行うのが必須です。
しかし、借り入れをせずに自己資金のみで新築を建てる場合は、抵当権を設定する必要がないため、必要な登記が行われずに放置されている場合があります。
そのため、相続や建て替えに伴って、登記簿の確認が必要になった時に、未登記建物であることが明らかになるケースが少なくありません。
未登記建物と固定資産税の関係
登記に関連する手続きや登記簿の管理は法務局の管轄です。一方、固定資産税の徴収は各地域の自治体が行っています。
そのため、自治体が独自に建物の調査を行い、所有者であると判断した人に対しては納税通知が送付され、納税の義務が課せられています。
固定資産税を払っていても登記済みの建物とは限らないのでご注意ください。
未登記建物の解体工事は可能
建物が未登記であっても取り壊し工事を行うことは可能です。
ただし、工事の前に建物の所有者を明確にしなければならない点や、通常とは届け出が異なる点などいくつか注意が必要です。
相続人全員の同意が必要
例えば、未登記建物の所有者が複数にわたる場合は、取り扱いに関して所有者全員の同意が必要になります。
もし、対象の建物を取り壊すことが明らかで、相続人が複数考えられる場合は、事前に行われる「遺産分割協議」の際に物件の取扱についても詳細に決めておきましょう。
家屋滅失届が必要
通常、登記済みの建物を取り壊した場合は、「建物滅失登記」を法務局に申請します。これを受け、法務局は登記簿の情報を更新し、固定資産税の調整を行っている管轄の自治体にも通知を行います。
しかし、未登記の物件はそもそも登記簿に記載がないため、法務局に建物滅失登記を申請することができません。そのため、未登記建物を取り壊した場合は、管轄の自治体に「家屋滅失届」を申請します。
もし、家屋滅失登記の届け出を怠ってしまうと、その後も取り壊し済みの物件が固定資産税の課税対象になってしまう恐れがあるので必ず行うようにしてください。
権利問題のトラブルを引き起こす可能性もある
権利関係の詳細がわからないまま未登記の建物を壊してしまうと、後から所有者を名乗のる人が現れた時にトラブルになってしまう恐れがあります。
最悪の場合、建造物損壊罪などの罪に問われ、5年以下の懲役が科せられる可能性もあります。
そのため、未登記建物を取り扱う際は、事前に全ての相続人で話し合いを行って「遺産分割協議書」を作成し、所有者を明確にしておきましょう。
原則としては、「遺産分割協議書」をもとに、法務局で「表題登記」を行った後、「所有権保存登記」を申請することで所有権を登記することができます。
とはいえ、建物の登記には費用が掛かるので、明らかに所有者の候補がない場合などは、建物を取り壊した後に「家屋滅失届」のみを行うケースが少なくありません。
未登記建物の調べ方
対象の物件が未登記建物かどうかを調べる方法は主に2つあります。
固定資産税納税通知書を確認
建物が登記されている場合は、法務局の登記官により「家屋番号」が定められています。そのため、固定資産税を納付している場合は、納税通知書に同封されている課税明細書の建物所在地欄に、「家屋番号」の記載があるかどうかで登記の有無を確認することが可能です。
もし、家屋番号の記載がない場合は、未登記建物である可能性が高くなります。ただし、万がいち記載漏れのケースもあるようなので、後述する法務局で直接確認する方法が確実です。
法務局で全部事項証明書の交付申請を行う
管轄の法務局で対象となる建物の「全部事項証明書」が取得できる場合は登記済みの建物といえます。なお、全部事項証明書が取得できない場合は、開示する情報がないため未登記の建物である可能性が高いです。
ちなみに、ごく稀に区画整理などが原因で、登記情報が更新されておらず全部事項証明書が取得できないケースがあります。こうした場合は、「登記済権利証」と呼ばれるいわゆる「権利証」などから、登記情報を再度確認することが可能です。
相続した建物が未登記だった場合は
未登記の建物を放置したままにしていると、いつまでも建物の活用ができず取り扱いが難しくなってしまいます。
相続した建物が未登記だと分かった場合は、速やかに所有者を明確にするための手続きを行いましょう。
所有者変更届を提出する
未登記の建物が相続されたとしても、地域の自治体は所有者を把握することができません。その結果、固定資産税の納税通知を可能性がある複数の相続人に対して送ってしまう場合があります。
このような状況を防ぐため、未登記の建物を相続したら、まず「所有者変更届」を管轄の市区町村に提出して、現在の所有者を通知します。
なお、届け出の際は「遺産分割協議書」と「相続人の印鑑証明書」が必要です。
未登記のままにしておくデメリット
自治体へ「所有者変更届」をしただけでは登記にはなりません。
相続した建物をその後も活用したり、売却したり、しばらく放置する予定がある場合は、登記をしていないことによるデメリットが生じる可能性があります。
所有権を証明できない
未登記建物が借地に建っているケースで、地主から立ち退きなどを要求された場合、本来は「建物買い取り請求権」を行使して建物を買い取ってもらうことができますが、未登記の場合は所有権を証明できないので権利を行使することができません。
そのため、立ち退きの場合であっても建物の取り壊し費用を、自己負担して土地を返却する必要があります。
過料に処される可能性がある
令和6年の4月1日に不動産登記法が改正されたことにより、不動産を相続した所有者は3年以内に相続登記を行うことが義務付けられました。これにより、違反した場合は10万円以下の過料の対象となるのでご注意ください。
融資を受けにくい
未登記の建物は抵当権を設定することができないので、建て替えやリフォームに伴って建物を担保にした住宅ローンを組むことができません。
未登記のままでは、自己資金でリフォームや建て替えを検討する必要があります。
売却が困難になる
未登記建物だからといって売却できないという法律はありません。しかし、未登記の状態では建物を担保にいれることができないので、新しく購入した方は住宅ローンを組むことができません。
また、購入者が後に登記をすることも可能ですが、そういった物件を好んで購入する方は限られる可能性があり、結果的に売却が困難になってしまう恐れがあります。
まとめ未登記建物を取り壊す時は
未登記建物を取り壊す際は、事前に所有者を明確にしたうえで、権利関係に注意しながら、慎重に工事の計画を立てていきましょう。
また、未登記建物は取り壊し工事の後に、「家屋滅失登記」を自治体に届け出る必要があり、登記済の建物とは申請場所や内容が異なるのでご注意ください。
もし、未登記建物を放置してしまうとデメリットが発生する恐れがあるので、相続した場合はなるべく早期に取り壊しを行うか、登記を済ませて運用するなど早めに方針を検討しましょう。