愛知県名古屋市では、住宅密集地にあり、老朽化などによって倒壊の恐れがある危険な空き家を除却する際に、費用の一部を負担する「老朽木造住宅除却助成」を実施しています。
なお、補助金額は最大で40万円です。この記事では、補助金額や対象条件などを詳しく解説しているのでぜひ参考にしてみてください。
そのほか、名古屋市では「ブロック塀等撤去費助成」など、付帯工事に関する補助制度があります。合わせてチェックしてみてください。
愛知県名古屋市で利用できる空き家の解体に関する補助制度
愛知県名古屋市では、市内の木造住宅密集地域にある老朽化が進んだ住宅を除却する際に費用の一部を負担する取り組みを行っています。
支給金額と申請期限
補助金額は対象住宅の延べ床面積1㎡あたり9,600円を掛けた金額を限度として、要した工事費の1/3です。また、上限は40万円となっています。
なお、受付期間は明示されていません。ご利用を検討している方は担当窓口にてご確認ください。
申請の条件
市内の木造住宅密集地域に存する住宅で、以下の要件を全て満たすものが対象です。
- 昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅で、登記事項証明書等に「住宅」または「共同住宅」の記載がある
- 現に居住に供している、または申請日より1年以内に居住用として供していた
- 既に耐震診断を実施している場合は、判定地が1.0未満または得点が80点未満と判定されており、耐震に係る補助等を受けていない
なお、補助金の申請前に工事に着手した場合は補助の対象になりません。申請は必ず工事に着手する前に行ってください。
申請の対象者は、当該住宅の所有者で市の固定資産税および都市計画税を滞納していない方に限ります。
その他、申請方法やご不明点は「住宅都市局都市整備部市街地整備課総括係」にお問い合わせください。
住宅都市局都市整備部市街地整備課総括係
【所在地】
〒460-8508
愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号
【お電話】
052-972-2752
【ホームページ】
補助金情報の詳細はこちら
補助金を申請したい方は解体無料見積ガイドへ
当協会が運営する「解体無料見積ガイド」では、建物の解体に伴う補助制度に関して、これまで3,500件以上のご案内実績があります。
地域ごとに専任のスタッフが丁寧に対応させていただきますので、申請をするのがご不安な方はぜひお気軽にご相談ください。
住宅の除却に関連した補助制度
名古屋市では住宅の除却に関連したその他の補助制度が設けられています。
ブロック塀の撤去に関する補助制度
名古屋市では地震などの影響による倒壊や転倒を未然に防ぐため、道路に面する高さ1m以上のブロック塀の撤去に対して、費用を一部負担する取り組みを行っています。
対象となるのはコンクリートブロック、レンガ、大谷石等の組積造の塀、またその他これらに類する塀で門柱等を含みます。ただし、隣地との境界部分に設置されている塀は対象になりません。
なお、補助金額は実際に要する費用、もしくは当該ブロック塀1mあたり6,000円を掛けた金額のうちいずれか少ない額の1/2で、上限は10万円です。
そのほか詳しい情報は名古屋市のホームページからご確認ください。
参考 名古屋市:ブロック塀等撤去費助成(暮らしの情報)名古屋市愛知県名古屋市で業者をお探しなら解体無料見積ガイドへ
補助金の利用にあたり名古屋市内の業者さんをお探しの方は、ぜひ「解体無料見積ガイド」にご相談ください。
当協会が運営する「解体無料見積ガイド」では、建物の解体や除却に伴う工事を検討されている方にお近くの業者さんを無料にて最大6社ご紹介しています。なお、ご紹介するのは当協会の厳しい選定基準を満たした優良な業者さんたちです。
これまでご利用いただいた7万5,000件以上のお見積り実績をもとに、地域ごと専任のオペレーターがお客様の条件にあわせて最適な業者さんをご案内しますので、ぜひお気軽にご相談ください。
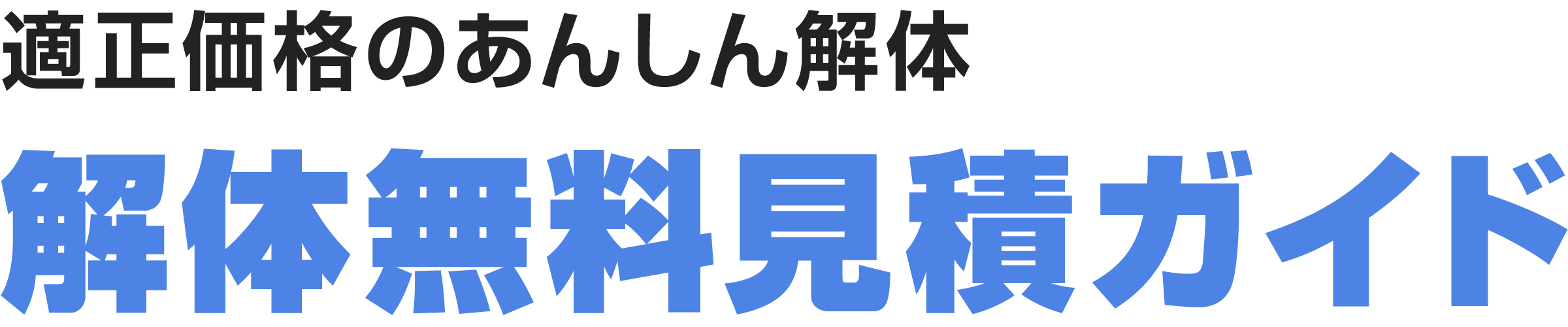


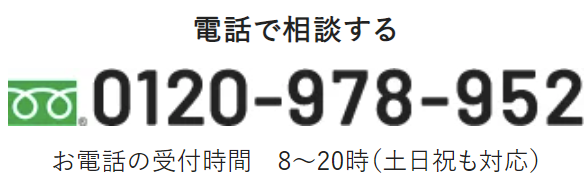
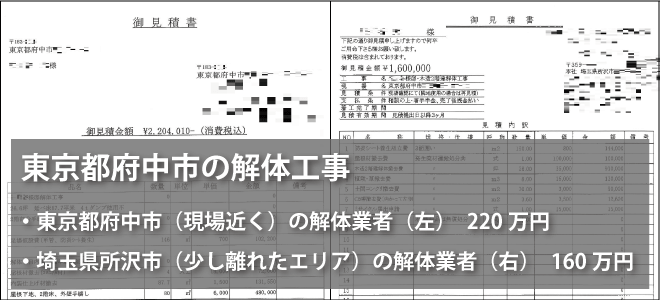
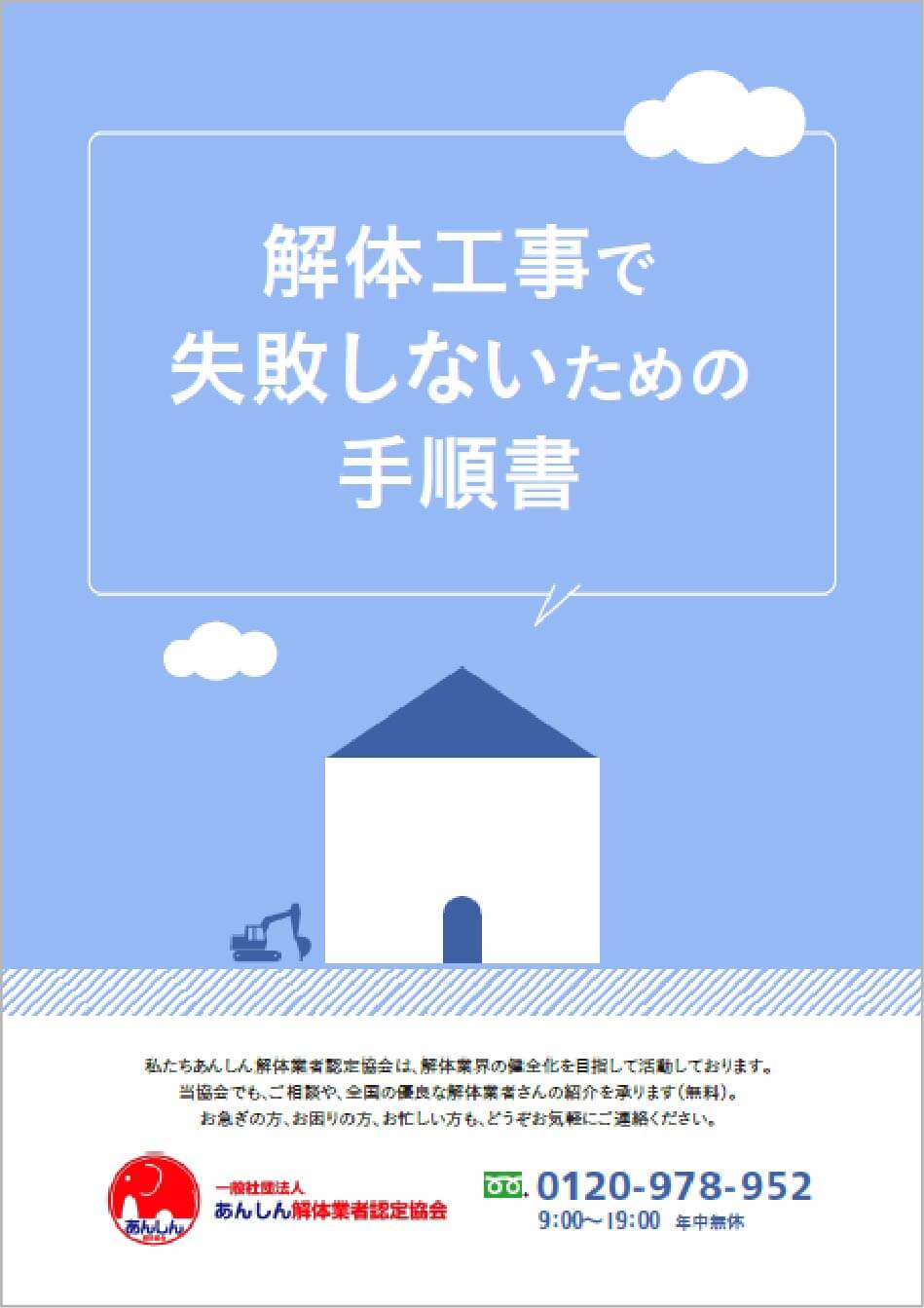
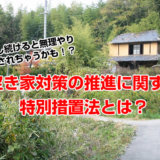

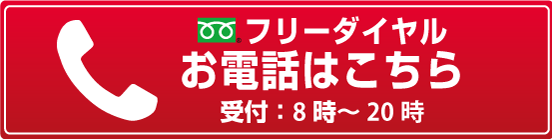
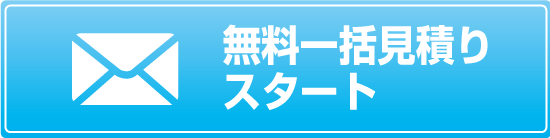
コメントを残す