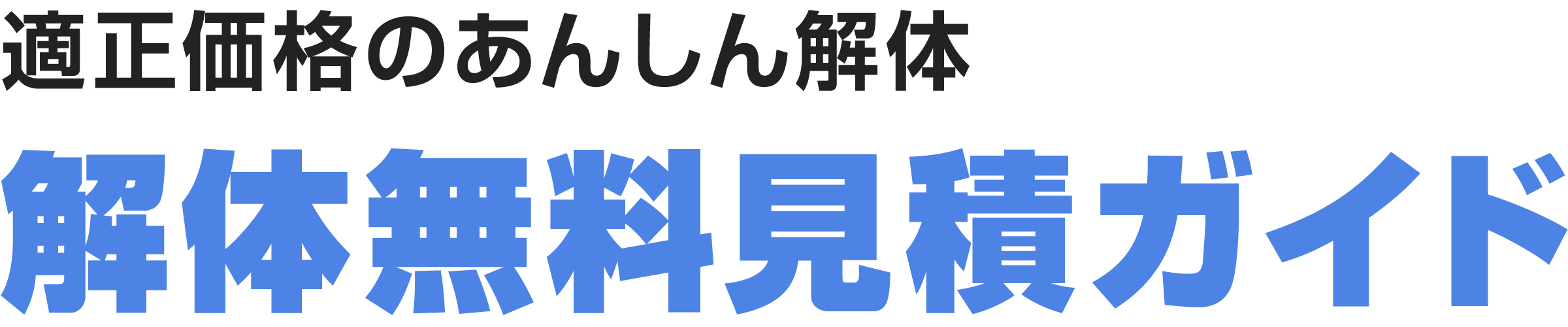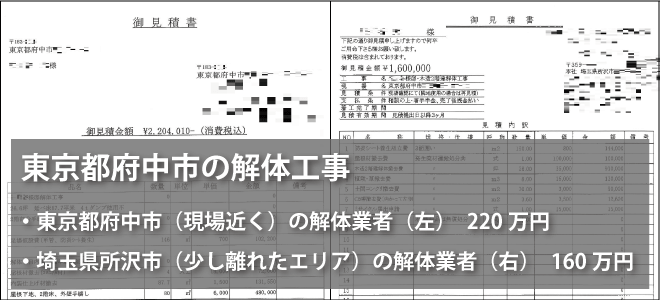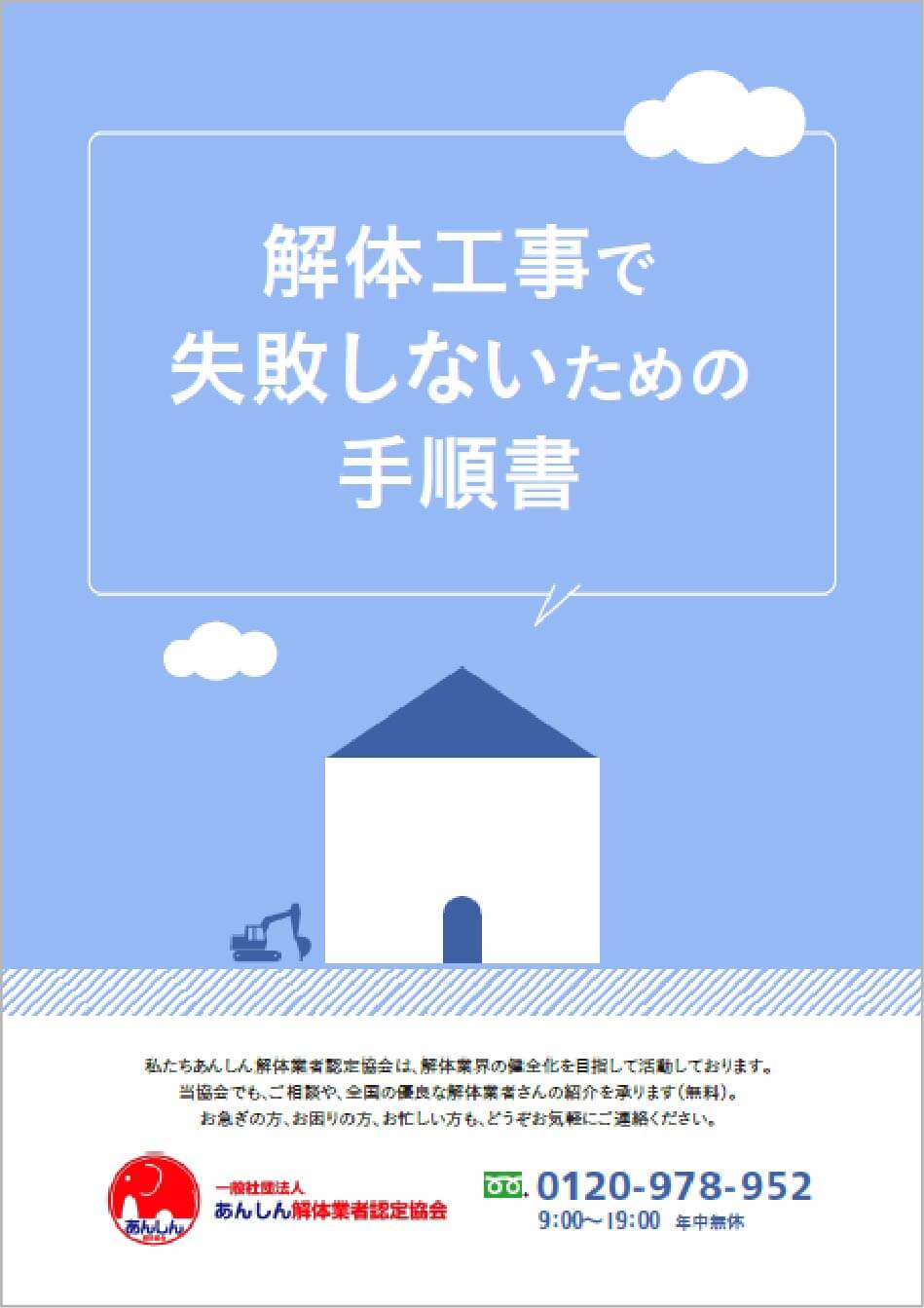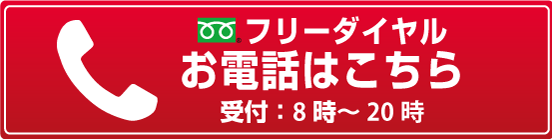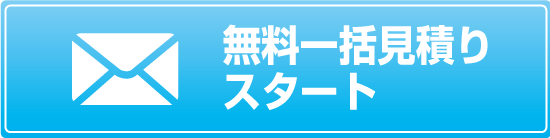転勤や介護などで、現在の持ち家から離れる必要に迫られた時、私達には何が出来るのでしょうか。
方法のひとつに、家を解体してから材料を運び、別の土地で建て直す「移築解体工事」があり、近年古民家の再生方法として注目されています。
しかし、一般住宅で移築工事を行う際は古民家に比べて高額な費用が発生します。
本記事では、一般住宅ではどのようにして移築工事が行われるのか、また移築以外に持ち家を守る方法はあるのかを詳しく解説していきます。
1 移築解体工事は超高額!非現実的な金額とは
一般住宅の移築解体工事は、技術的には可能な方法です。
しかし、費用が高額なために事例がほとんど存在しないのが現状です。
移築解体工事は、解体工事→運搬→建設工事の流れで行われます。
建設工事の際は、再利用出来る建築材料がありますので、以前建てた時よりも安価で建てることは可能です。
しかし、解体工事と運搬にかかる人件費を考えると、以前の建設工事にかかった金額の1倍~1.5倍、場合によってはそれ以上の費用がかかります。
さらに、解体前と同じ設計、材料で建設を行うので、全ての工程を一社で行う必要があります。
そうなると、依頼する業者さんも極めて限定的になり、依頼が困難なのも現状です。
以上の点から、一般住宅の移築解体工事は現実的には難しく、事例も少ないのです。
しかし、中には現実的な移築工事も存在します。
現実的な移築工事とは
もちろん、全ての移築工事が超高額な訳ではありません。
特定の状況下では、建設時の金額以下で移築が出来る場合もあります。
曳家移築

曳家(ひきや)工事は、家を基礎から引き剥がし、そのままレーンに乗せて移動させる工法です。
家を解体する必要が無いので、工期も短く済みます。
ただし、曳家工事は移築先の距離が近い事が条件です。
当然、レーンを引いて県境を超えたりはできません。
主に、日当たりの調整や、地盤の沈下を修正させるために行います。
吊り上げ移築

吊り上げ工事も解体をせずに家を移動させられる工法で、クレーンで建物を丸ごと持ち上げ、目的地まで移動させます。
当然ですが、吊り上げ工事も移築先が近い事が条件です。
目安としては、隣接する土地区画までだと思ってください。
つまり、一般住宅は遠方の移築には向いていないのです。
では、マイホームは空き家のままにするしか無いのでしょうか?
そんなことはありません。
続いては、空き家になってしまった建物の利用方法を見ていきましょう。
2 空き家になった住宅はどうする?【活用編】
空き家になってしまった持ち家を放置しないために出来る事を見ていきましょう。
まずは、持ち家を活用して利益を得る方法からご紹介します。
売却をする
今の土地に戻る予定が無く、建物の管理にかかる費用を心配される場合は、売却も一つの手です。
売却をするなら状態の良い現在が一番高額で売買できるので、タイミングとしては申し分ありません。
しかし、当然ながら一度売ってしまうと、再び住みたい、活用したいと思っても取り戻す事は出来ません。
売却前には、下記の記事も参考に検討してみてください。
賃貸として貸し出す
もちろん、せっかく建てたマイホームをそう簡単に手放したくない方もいます。
売却がためらわれる方は、賃貸としての貸し出しもおすすめです。
賃貸物件として貸し出せると家賃収入が入りつつ、空き家状態を回避出来るうえに、戻って来た時にはまた住むことができます。
とは言え、維持費や管理費は当然所有者であるあなたが払いますし、入居者が見つからなかった場合は空き家同然になってしまうリスクもあります。
また、人が住む以上建物は傷んでいきますので、自分の思うように建物の状態を管理することも出来なくなるので注意してください。
3 空き家になった住宅はどうする?【維持編】
将来的にマイホームに戻ってくる、住む予定がある場合は、建物を維持する必要があります。
空き家になってしまうと家はどんどん状態が悪くなりますし、賃貸にしてしまうとどうしても建物が傷んできます。
将来住むために資産価値を下げたくないなら、継続的なメンテナンスをおすすめします。
家を維持するには継続的なメンテナンスを!
建物を維持していくには、将来戻るまで継続的に建物のメンテナンスをする必要があります。
そのため、定期的に掃除や設備の点検をする必要があるのです。
メンテナンスは、月1回以上の頻度が最低限とされています。
メンテナンスと言われても何をやったら良いか分からない方は、3大メンテナンスを基準にメンテナンスを行うと最低限の環境を保てるので、ぜひ参考にしてみてください。
| 3大メンテナンス | |
|---|---|
| 換気 | 空き家内の空気は、極端に流れが悪くなっています。ただ玄関の扉を開けるのではなく、押入れやクローゼットなど、湿気が溜まりやすい場所もしっかり換気をしましょう。 |
| 通水 | 水道管は、あまりに使わないと錆びてしまいます。また、錆によって水道管が破裂する恐れもあるので、メンテナンスの際は必ず水道から水を流しましょう。1分程度流しっぱなしにして、水に錆や汚れが混じっていなければOKです。 |
| 掃除 | 室内の掃き掃除はもちろん、庭の手入れも重要です。雑草が生い茂っている状態では、害虫の住み家になってしまいますし、伸びすぎると近隣にまで迷惑がかかります。 |
メンテナンスは依頼もできる
とはいえ、空き家のメンテナンスに行くのが難しい方もいらっしゃると思います。
自身で管理が出来なくても大丈夫です。
メンテナンスを代行してくれる「空き家点検サービス」に依頼する方法もあります。
サービス会社によって内容は変わりますが、主に室内の掃除と設備の点検を行います。
空き家点検サービスのひとつに、NPO法人が運営する「空家・空地管理センター」があります。
簡易的な管理内容でお手軽に依頼できる「100円管理」から、将来のために資産価値を下げたくない方へ向けた「しっかり管理」まで用意してある、オススメの業者さんです。
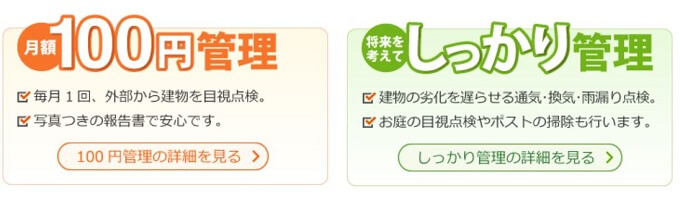
空き家が遠方にある場合は、交通費もかかってしまうので、むしろ依頼した方が安く済むケースもあります。
メリット、デメリットを把握した上で検討してみてください。
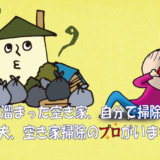 空き家掃除は自分で行う?大変な時は遺品整理業者に依頼しよう!
空き家掃除は自分で行う?大変な時は遺品整理業者に依頼しよう!
もう一つの住まい『セカンドハウス』
持ち家を空き家にしてしまうと、固定資産税の軽減措置が外れてしまうのを懸念されている方も多いのではないでしょうか。
しかし、建物が空き家とみなされると、固定資産税の軽減措置が外されてしまうのです。
軽減措置では、固定資産税が1/6まで免除させるので、軽減が外されると実質的に固定資産税が6倍になります。
 空き家を放置すると損する税制を紹介!制度の仕組みと対処法は?
空き家を放置すると損する税制を紹介!制度の仕組みと対処法は?
支払う税金を上げたくない方は、建物をセカンドハウスとして利用するのがおすすめです。
月に1回以上、居住用として使用しているかが基準です。
平たく言えば第二の家として利用すれば良いのです。
別荘と混合されやすいですが、厳密には異なります。
別荘はあくまで「保養のため」に建てられたもので、生活に必須な建物とはみなされません。
しかし、セカンドハウスは「月1回以上」居住用に使用することで、生活に必須な建物とみなされ、一般住宅と同様に固定資産税の軽減措置が適用されます。
セカンドハウスとして利用する場合もメンテナンスは欠かせませんが、建物が遠方でなければ検討されてみてはいかがでしょうか。
メンテナンスだけじゃない!意外な維持費用とは
空き家を管理する場合、メンテナンスの手間だけではなく維持費用もかかります。
以下は、建物の維持にかかる費用のまとめです。
| 固定資産税 | 先程お話した通り、固定資産税はかかり続けます。セカンドハウスとして利用しない場合は従来の6倍もの金額を支払わなくてはなりません。 |
|---|---|
| 都市計画税 | 都市開発の為に建物や土地の所有者にかかる税金。都市計画税にも固定資産税と同じく軽減措置がありますが、空き家とみなされた場合は軽減措置が外されます。 |
| 火災保険 | 必須ではありませんが、無人状態の建物は放火される可能性が高まるので、火災保険への加入も行う必要があります。 |
| 水道光熱費 | 訪問、メンテナンス時の為に水道や電気、ガスの契約は解除しないのが一般的です。もちろん使用量は少ないので高額にはなりませんが、一切使用しなくても基本料金は必ずかかりますので注意してください。 |
人が住んでいなくても、建物を維持していくには様々な費用がかかります。
以下の記事では、空き家になった建物を維持するための費用について詳しくお話しています。
維持費用も考慮に入れた上で、建物の維持をご検討ください。
 空き家の維持費用は高額!あなたが出来る最善の選択とは
空き家の維持費用は高額!あなたが出来る最善の選択とは
4 まとめ
やむを得ず持ち家から離れる事になった場合は、移築工事はかなりの高額費用がかかるので現実的ではありません。
将来的にまた持ち家で生活をする予定であれば、手間と費用を覚悟してでも維持に努めるのが賢明です。
しかし、費用面や手間を気にするのであれば、売却なども一つの選択肢ではあります。
移築工事や空き家の管理について、疑問や悩み事がある場合は、当協会が運営する解体無料見積ガイドまでご連絡ください。
お悩みの解決に尽力させて頂きます。
TEL:0120-978-952(携帯・PHS 可)
受付時間: 9:00~19:00(日曜・祝日除く)