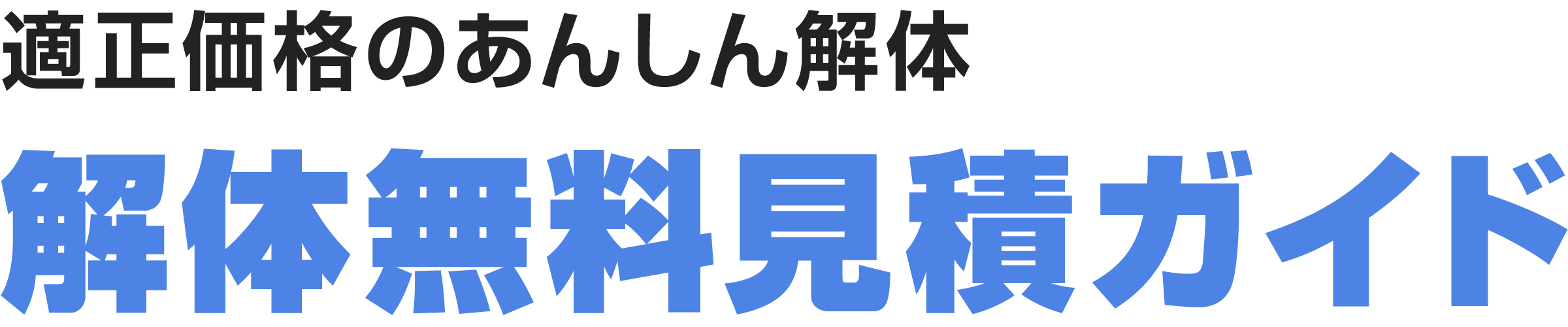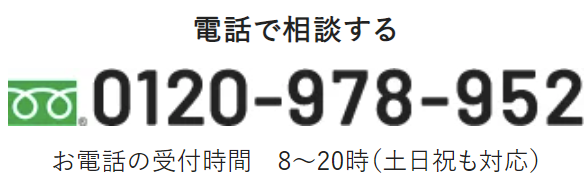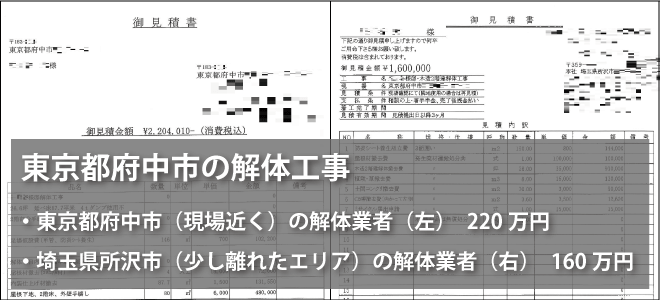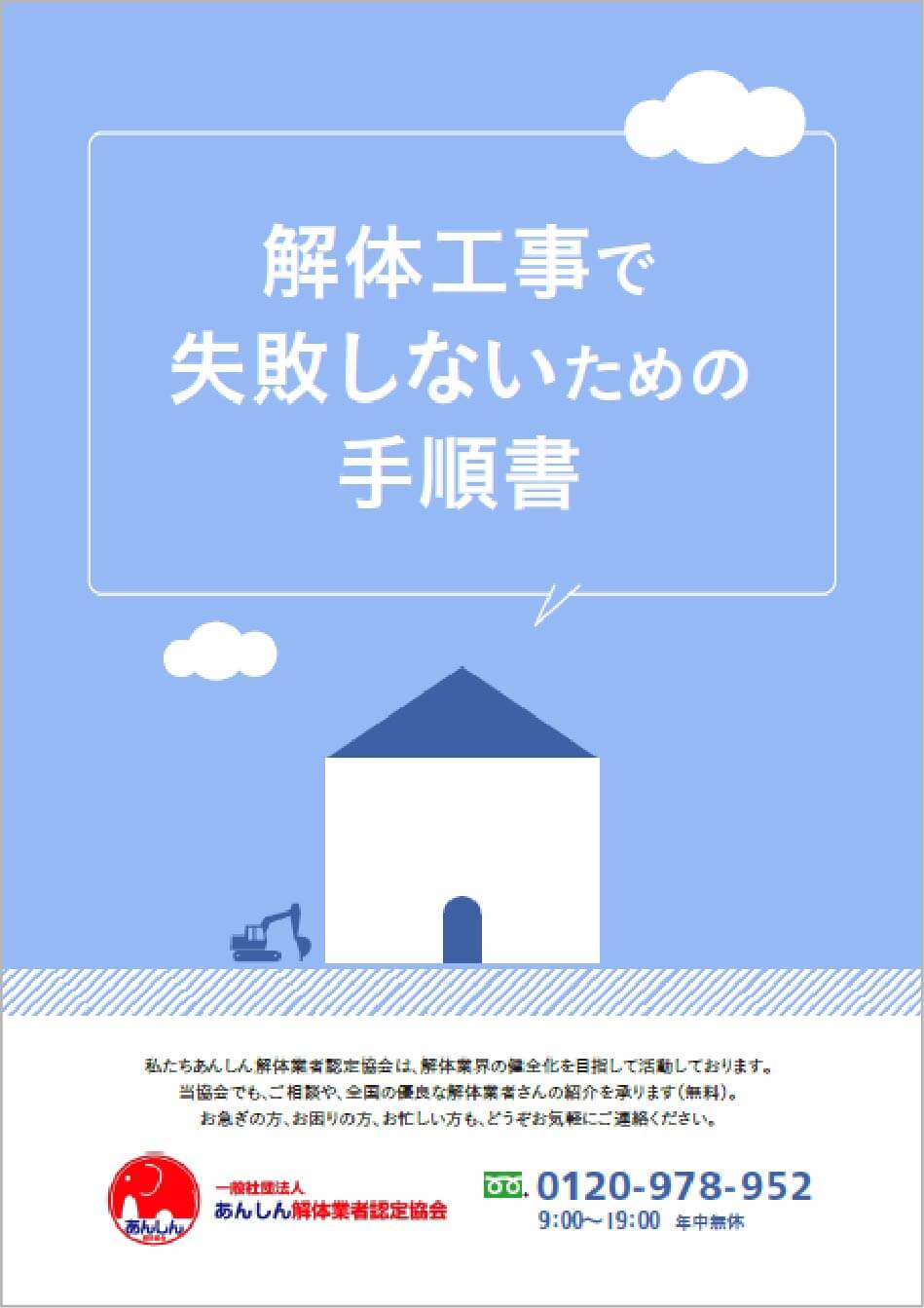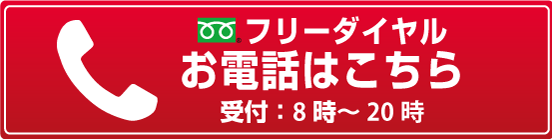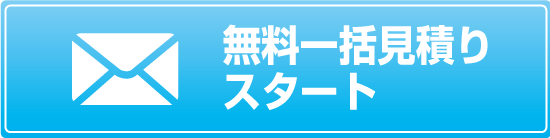茨城県日立市には、解体や除却に関する補助金・助成金が設けられています。
本記事では、空き家の解体やリフォーム費用を補助する制度を詳しく解説しているので、ぜひ参考になさってください。
茨城県日立市で利用できる空き家の除却に関する補助制度
日立市には、老朽化した空き家や危険な空き家の除却に必要な費用を一部を負担する「空き家解体補助金(利活用型)」を設けています。
| 項目 |
空き家解体補助金(利活用型) |
| 補助金額 |
補助対象経費×1/3 |
| 補助限度額 |
50万円 |
| 申請期間 |
|
| 申請条件と申請対象者 |
対象の空き家は、戸建または併用住宅であること
対象の空き家は、1981年5月31日以前に建築確認を受けて建築されていることこと
対象の空き家は、公共事業の補償対象となっていないことこと
対象の空き家は、不動産業を営む者が営利目的として所有しないこと
対象の空き家は、特定空家等でないことこと
対象の空き家は、解体する時点で、1年以上居住用として利用されていないこと
対象の空き家は、所有者等が死亡した後に居住用として利用されていないこと
対象の空き家は、延べ床面積が50㎡以上であることこと
対象の空き家は、公共事業の補償対象となっていないこと
申請者は、本事業は市税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料及び介護保険料の滞納がないこと
申請者は、暴力団員と認められていないこと
申請者は、共有名義の場合は全ての共有者から空き家解体の同意を得た者であること
申請者は、所有者の相続人であること
申請者は、空き家の敷地を取得または賃借した者であり空き家の所有者から空き家の解体について同意を得た者であること
申請者は、不在者財産管理人、成年後見人等公的機関が発行した書類によって対象となる空き家を処分する権限があると認められる者であること
除却工事は、空き家及び空き家に付随する門塀等の工作物、敷地内の樹木等を除却し原則更地にする工事であること
除却工事は、日立市内に本店か営業所がある法人または個人事業者が行うこと
除却工事は、解体にかかる費用が50万円以上あること
除却工事は、建設業法に掲げる土木工事業、建築工事業、解体工事業の許可を受けた者であること
除却工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律により解体工事業者の登録を受けた者であると
|
| お問い合わせ先 |
日立市役所 都市建設部都市政策課住政策推進室 |
| 住所 |
〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 |
| 電話番号 |
0294-22-3111 |
| ホームページURL |
https://www.city.hitachi.lg.jp/index.html |
補助金の利用にあたり解体業者をお探しなら解体無料見積ガイドへ
補助金の利用にあたり解体業者をお探しの方は、ぜひ「解体無料見積ガイド」にご相談ください。
当協会が運営する「解体無料見積ガイド」では、建物の解体や除却に伴う工事を検討されている方にお近くの解体業者を無料にて最大6社ご紹介しています。なお、ご紹介するのは当協会の厳しい選定基準を満たした優良な解体業者です。
これまでご利用いただいた10万件以上のお見積り実績をもとに、地域ごと専任のオペレーターがお客様の条件にあわせて最適な解体業者をご案内しますので、ぜひお気軽にご相談ください。
年間9,000件以上のご相談を承る地域専任スタッフが即日対応。