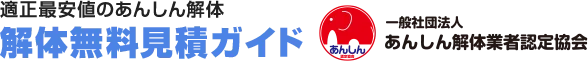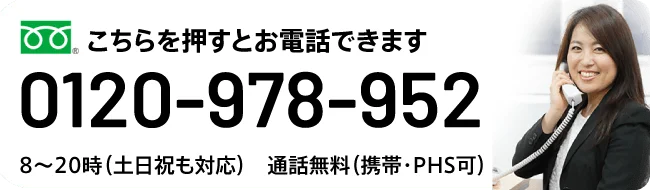解体工事内容に関する基礎知識
工事の安全対策について
安全対策に関しての知識と対策

建設業における労働災害は多く、建物の撤去工事でも様々な事故が発生しています。しかし多くのお施主様は、実際に事故が起きるまでは自分とは無関係のことに思ってしまうものです。
もちろんお施主様ご自身が工事を行うわけではありませんが、万が一、工事中に事故が発生してしまった場合には、近隣住居への賠償責任も問われることになりかねません。
工事における事故を防ぐためにも、過去の事故事例から学び知識をつけることも必要で、また事故を起こすような業者を選ばないように、業者を選ぶ際は安全対策がきちんとされている業者かどうかを確認することも重要です。
安全に工事を済ませられるように、ここでは工事の安全対策に関しての知識と対策を詳しくご紹介します。
建物の撤去工事における事故の種類
建物の撤去工事は危険と隣り合わせの作業であり、近年でも痛ましい事故が多く起きています。
もしもお施主様の撤去工事で近隣住民へ被害があったら…と考えただけで恐ろしいですよね。撤去工事において過去にどのような事故が起きているのかをまずはご紹介します。
壁や建物の崩壊による住宅の破損、人への被害

建物の種類や立地にもよりますが、一般的に撤去工事では、騒音や落下物防止などを考慮して内側から取り壊しを行い、外壁を後に壊す流れが推奨されています。
しかし、安全に配慮されていたはずの外壁が崩壊し、隣の建物に被害を及ぼす事件が近年でも発生しています。 建物や壁の崩壊は、住居の破損だけではなく住民にまで被害が及ぶケースもあります。
2010年には岐阜市で工事中に外壁が倒れ、下校中に下敷きとなった女子高生が死亡した事故がありました。
業者は外壁の転落を防ぐためのワイヤ固定による転倒防止策や、警備員を配置する等の安全対策を怠っていました。
このように工事価格を下げるために安全性を欠いたことが原因となり、あってはならない事故を引き起こしてしまいます。工事現場における外壁崩落による事故を受けて、下記の国土交通省によるガイドラインが設けられています。
車輌や重機との衝突・横転

撤去工事では、建物を取り壊すためショベルカーなどの重機を使用します。最近の撤去工事では、大型で強力な重機が使用されるようになり、作業員に一層高い技術が求められています。
2015年5月には、東京都墨田区の工事現場で重機の転落により、作業中の男性が操縦席に閉じ込められ死亡しました。
足場が悪く狭い空間で作業をする現場は、多くの危険と隣り合わせです。作業主任者による明確な工事手順の計画と伝達・作業員全員への安全指導と現場管理が事故を未然に防ぐために必ず必要です。
また公道において、撤去工事に使用する重機や車との衝突事故も発生しています。工事中には監視員を配置しますが、人員削減などが理由で必要な作業員を置かなかったことが原因で事故を引き起こしてしまったというケースもあります。
足場からの転落事故

高所で作業を行う工事は転落の危険と隣合わせです。
撤去工事の現場で足場が崩れ、作業員が転落してしまう事故が起きています。足場からの転落事故の原因の一つは、作業員の過労や足場の強度不足と言われています。
工事による事故で最も被害に遭う確率が高いのは工事にあたる現場の作業員ですし、作業員が怪我をしてしまえば、結局作業を中止することになり工期は遅れてしまいますから、お施主様にも被害が出ます。
豪雨や強風による事故

工事費用を抑えるためには、短い工期で作業を行うことも必要です。しかしコスト削減を図り、作業を中止した方が良いような悪天候の中でも、作業を強行してしまう業者も中にはいます。
豪雨や強風の中で作業を行うと、足を滑らせたり、風に煽られて足場から転落してしまう可能性もあります。
また台風等の強風の影響で最も恐ろしいのは、危険物が飛んでしまい、建物や人へぶつかってしまうことです。強風に煽られて撤去工事現場の足場が倒れたり、養生パネルが剥がれたり、家屋の一部が破損してしまう危険性も十分に考えられます。
強風の中作業を強行してしまえば、重機のコントロールが難しくなり、近隣家屋にぶつかったり、破損させたりしてしまう可能性もあります。ただでさえ慎重さが求められる作業ですから、少しでも天候が不安定な場合には施工を中断し、また、現場を離れる際にも倒壊・破損などの対策を施さなくてはなりません。
国で定められている安全対策

痛ましい事故を起こさないためにも、工事現場において安全面に関する決まりがあります。
撤去工事における安全対策として、国からどのような法律やガイドラインが出されているかに関してご説明致します。
労働安全衛生法と労働安全衛生規則
工事現場では、国や行政から法律や省令で安全面の対応を義務付けられています。工事に関する法律・省令として「労働安全衛生法」と「労働安全衛生規則」が存在します。
労働安全衛生法
労働災害を防ぐよう労働者の安全と健康を守り、快適な職場環境を作ることを目的とした法律です。労働災害の防止対策・労働者の危険を防止する為の措置・機械や危険物に関する決まり等について定めています。
労働安全衛生規則
労働安全衛生法に基づいて、労働の安全衛生について決めた規則です。解体工事において特に関連する規定としては、アスベストに関する飛散防止の強化や、解体工事で使用する機械が規制対象になる等の改正がありました。解体工事の現場においても、前述のような法律や省令を守ることが事故防止につながります。
国土交通省のガイドライン
国土交通省は、事故を防止する安全対策として「建築物の解体工事における外壁の崩落等による公衆災害防止対策に関するガイドラインについて」を発表しています。このガイドラインは、静岡県富士市で起きた建物の撤去工事の重大事故を受け、建設業者に向けた撤去工事における災害防止対策に関して記載されています。工事を行う上で法令を守る他に、以下の点において留意するよう呼び掛けています。
国土交通省は、事故を防止する安全対策として「建築物の解体工事における外壁の崩落等による公衆災害防止対策に関するガイドラインについて」を発表しています。
- 解体予定の建物の事前調査を行い、事故防止に配慮した工事の施行計画を作成すること。
- 解体工事の途中で、想定外の構造・設備上の問題が発生した場合は、工事を中断し計画の修正を検討すること。
- 公衆災害を防止するため、建築物外周が張り出している建築物・カーテンウォール等の外壁工事は、工事の実施や工法の選択に安全性を保つよう配慮する。
- 増改築部分や異なる構造の接合部の解体工事については、特に強度に配慮して計画の作成と実施を行う。
- 大規模な建築物の解体工事は、事故が発生した場合の被害の大きさや過失責任を十分認識し、解体工事計画と実施を行うこと。
- 建築物の設計図は、解体工事の際安全性の検討に重要であるため、保存・継承に努めること。
国土交通省から出ている詳しい内容はこちらから御覧ください。
安全性を考慮した作業工程

法律に基づき安全と健康を守るため、工事現場では様々な対策が行われています。
危険を伴う工事だからこそ、予測をもとに準備を徹底したうえで計画に沿った工事を行うことが重要です。
危険予知活動(KY活動)
事故を未然に防ぐため、現場では工事前に危険を予測して、どう対処すべきかを想定する危険予知活動(KY活動)が行われています。業者ごとに細かい内容は異なりますが、KY活動は主に次の流れで行われます。
足場と養生による安全対策

なんといっても最も安全性が必要とされるのは足場です。強風の際に倒壊することがなくても、風や雨にさらされて弱まってしまった足場は、その後の施工中に作業員へ危険を及ぼすかもしれません。
強風にも耐えられるための対策としては、ワイヤーで建物と足場をつなぐ倒壊防止対策や、足場用の接続金具にはより頑丈なものを選んで強度を安定させるなどがあります。
また、足場に関して取り決められている労働安全衛生規則では、平成27年に足場からの墜落防止措置が改正されました。改正された労働安全衛生規則の概要は以下の通りです。
強風が予想される際は風の通り道を作る

粉塵などの飛散物を防ぐため、足場を囲うようにして設置する養生シート。しかし、入ってきた風の抜け道を養生シートがなくしてとじこめてしまうことで、足場を揺らしてしまう危険性があります。
もちろん、かといって養生シートをすべて撤去してしまうと、粉塵の飛散など別の被害を生んでしまう可能性もあります。悪天候が予期されるときのみ出隅部分の養生を絞る・撤去するなどの対策が必要です。
また、防音パネルなどのパネル養生は取り外しが難しいため、組み立ての段階から全面パネル養生にするのをやめ、一部を防音のシート養生にするなどすると、風を足場に留めない抜け道を作ることができます。
損害賠償保険

起こってはならないことですが、もしも事故が起きてしまった場合に備え、損害賠償保険に加入することは重要です。 しかし業者によっては未加入の業者も多いのが現状です。
通常、何か事故が起きた場合の責任は業者がとりますが、例外的に依頼主であるお施主様自身の責任が問われるケースもある為、必ず業者に保険へ加入しているかの確認を行いましょう。
建物の撤去工事は一般の工事に比べて事故が多いことから、建築関係の保険に加入していても、撤去工事における事故は補償から除外されていることがあります。
そのため業者を選ぶ際は、保険に加入しているかだけでなく、もし第三者へ賠償責任が起きたときに、補償がきちんと受けられる保険であるかについて聞くことが重要です。
また保険に加入していても、ほこりや振動・騒音に関する損害賠償は補償されない保険が多いです。トラブルを防ぐためにも、ご近所からの騒音等に関するクレームによる問題が起きないよう、ご近所へ事前の挨拶や工事中のしっかりした対応を行う業者を選びましょう。
損害賠償保険の種類と注意点

建設業に関わる保険には、建設工事保険・土木工事保険・組立保険などの保険が挙げられます。
しかし、撤去工事においてはこれらの保険は適用外とされるケースが多いのが現状です。建物の建築工事や増築・修繕工事は適用される保険が主ですが、撤去工事は事故の危険性が高いことから、対象から除かれてしまうのです。
そのため、事故に備える保険として「請負業者損害賠償保険」に加入する業者が多く見受けられます。請負業者損害賠償保険とは、請負した工事を行うにあたって、現場などで事故が起こり人や物に危害を加えてしまった場合に、被る損害について保証する保険です。
請負業者損害賠償の加入単位
請負業者損害賠償には、年間単位での加入・工事単位での加入・車両単位での加入の3つのタイプがあります。
加入する保険会社にもよりますが、会社や年間単位で加入するタイプ、工事の現場ごとに加入する工事単位での加入タイプ、工事で使用する重機やトラックなど、工事に関連する車両単位で加入するタイプがあります。
保険の対象外となるケース
請負業者損害賠償へ加入していても、内容によっては損害賠償保険が適用されない場合もあるため注意が必要です。特に、塵や埃・騒音に対する損害賠償は適用外となるケースが多いことを知っておきましょう。
建物の撤去工事では、建物を壊す際に塵や埃、重機による騒音や振動が起きることが予測できます。そのため、予測できる事態なので保険の適用外とされる場合が殆どです。
近隣住民とのトラブルを起こさないためにも、撤去工事前の近隣挨拶を丁寧に行うとともに、工事前に養生をしっかり施すこと・水撒きや清掃を徹底させて、トラブルを事前に防ぐことが重要です。
現場だけではなく、近隣への配慮も重要

また撤去工事における事故の事例や業者の予防策をご紹介してきましたが、工事では現場だけではなく、近隣への配慮も重要です。そのため、各業者は、近隣住居への騒音対策や廃棄物や埃の飛散流出に関しては、必要に応じて近隣への事前説明会を行ったり、車両誘導員の配置なども行って対応しています。
トラブルの中でも作業員の対応が原因で起こるケースもあります。工事をしっかり行うだけではなく、現場でもマナーを守り近隣住民への丁寧な対応ができる業者を選ぶ必要があります。
ですので、依頼する業者を選ぶときには、これら安全対策や近隣への配慮がきちんとしているかどうかを確認することも重要です。
安全対策の確認と同時に、もし事故が起こった際にどのような対応をしてくれるのかについても、具体的に聞いておくことをおすすめします。